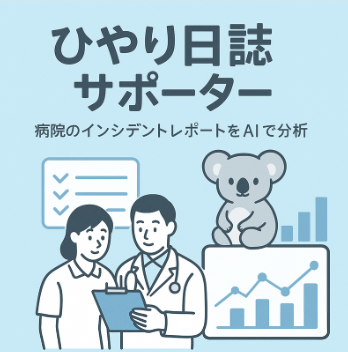医療現場では毎日のように「インシデントレポート」が積み上がっていきます。
転倒、誤投薬、器具の取り違え……その一つひとつが貴重な学びであり、次の事故を防ぐ手がかりです。
しかし現状では、この膨大なレポートを専従の看護師が手作業で分類・分析し、「医療安全ニュース」としてまとめて配布しています。労力がかかるうえに、ベテラン職員にとっては「何百回も見てきた同じ注意喚起」と感じてしまいがちです。情報が十分に届かないまま埋もれてしまうことも少なくありません。
発想の転換:AIで「完全個別化」する
私が提案するのは「ひやり日誌サポーター」という仕組みです。
AIがインシデントレポートを自動で要約・可視化し、医療者の職種・キャリア年数・関心に応じて最適化された形で届けるという発想です。
たとえば――
- 1年目の看護師には「点滴の刺し違え防止」の動画
- 10年目の臨床検査技師には「検体の取り違え」事例
- 20年目の医師には「クローブラ投与時の注意点」
といった具合に、必要な人へ必要な学びを、ちょうど良いタイミングで届けることができます。
配信の場所とタイミングも最適化
さらに重要なのは「動画の配信場所」。
電子カルテの画面上に直接30秒程度の短い動画として表示させることを想定しています。
例えば、外科医が手術を終えて病棟に戻り、カルテを開いた瞬間に「術後管理にまつわる安全情報」が流れる。
つまり、「誰が・いつ・何を学ぶべきか」をAIが判断し、アウトプットを完全に個別化できるのです。
日常業務の一部として根付く仕組み
もし病院にスタッフが400人いれば、毎日400本の最適化された動画が配信されます。
従来の「全員に同じ資料を配る」という方法ではなく、一人ひとりに合わせた学びを日常業務に埋め込むこと。これが医療安全の「新しい当たり前」になると考えています。
前提・分析・結論
前提
- 医療安全は日常的な学びの積み重ねで支えられている。
- 従来のレポート分析は膨大な手作業に依存している。
分析
- 情報の量に比べて、届け方・活かし方に課題がある。
- AIを活用すれば、個別化・タイミング最適化・省力化が同時に実現できる。
結論
「ひやり日誌サポーター」は、インシデントレポートの価値を最大化し、医療安全を“伝統的な負担業務”から“日常の自然な学び”へと変える仕組みになり得る。