金曜勉強会での一場面です。非結核性抗酸菌症(NTM)の原因菌として知られるMAC菌について話題になりました。MACとは、Mycobacterium avium と Mycobacterium intracellulare を合わせた呼び方です。
ただし、同じ日本国内でも、地域によって「どちらが多いか」は違います。
北海道ではアビウムが多い
非結核性抗酸菌症の原因菌を比べると、北海道ではアビウム(M. avium)が優勢です。割合としては、アビウム85%、イントラセルラーレ(M. intracellulare)15%。
九州ではイントラセルラーレが多い
一方で、九州では逆にイントラセルラーレが多く、アビウム40%、イントラセルラーレ60%という比率が報告されています。地域ごとに背景環境や感染経路が違うのかもしれません。
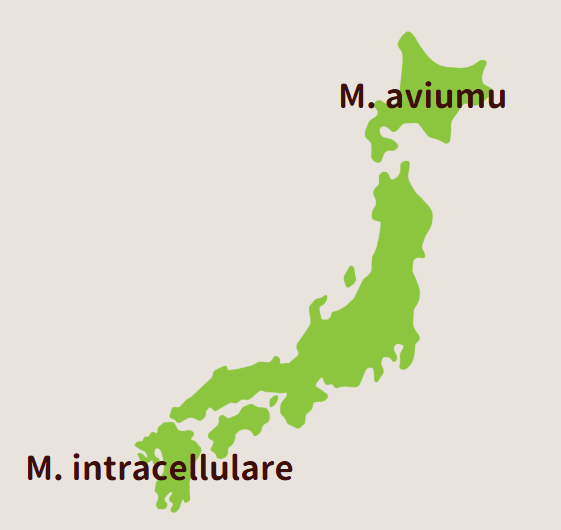
地域特有の感染症
非結核性抗酸菌症だけでなく、日本には地域ごとに多い感染症があります。
(1)エキノコックス症
北海道に集中。キツネが関わる寄生虫感染症です。
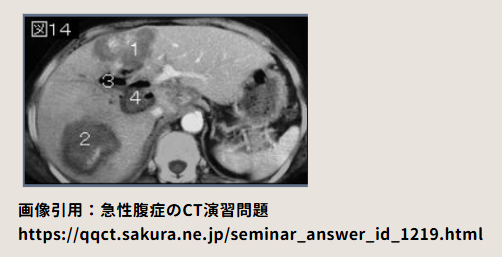
(2)つつが虫病
鹿児島県、福島県、千葉県などに多い。フトゲツツガムシが媒介します。
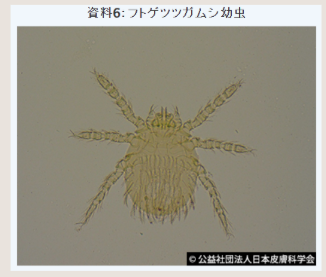
(3)HTLV-1とATL(成人T細胞白血病リンパ腫)
九州や沖縄に多い。母乳感染などによって地域に集積することが知られています。
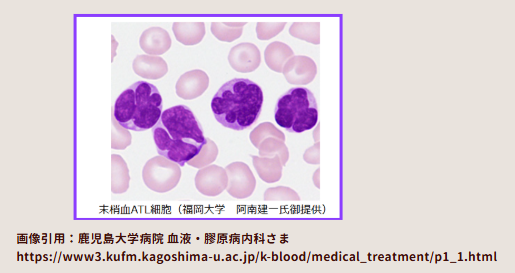
(4)バンクロフト糸状虫(象皮症の原因)
奄美大島などでかつて見られましたが、現在では新規発症はなくなっています。
秘書ユナのコメント
一見すると同じ「日本」という枠組みでも、実際には地域の自然環境や生活習慣によって、出会う病気の種類や頻度はかなり違います。臨床医としては「この地域では何が多いのか」を頭の片隅に置いておくことが診断の助けになります。
前提・分析・結論
前提
非結核性抗酸菌症を含め、日本国内でも地域によって多い病気が異なる。
分析
・北海道ではM. aviumが多く、九州ではM. intracellulareが多い。
・エキノコックス症は北海道、つつが虫病は鹿児島・福島・千葉、HTLV-1は九州・沖縄に偏っている。
・寄生虫疾患(象皮症など)は撲滅に近いが、過去の地域性は臨床経験として重要。
結論
診断の精度を高めるには、患者の「地域性」を意識することが不可欠。医師が知識として持っているだけでなく、現場で自然に思い出せるように訓練しておくことが望ましい。
