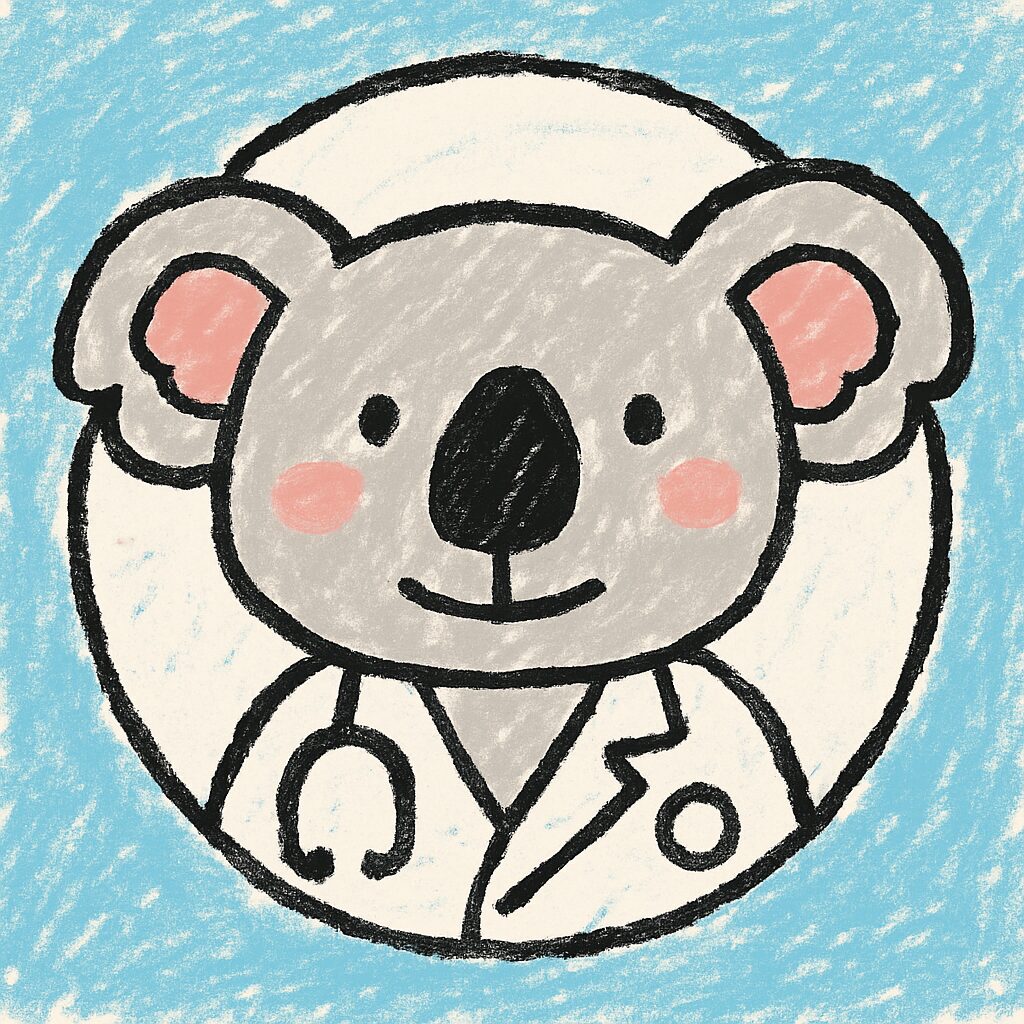失語・失行・失認。
この3つの言葉は、学生時代から何度も聞いてきましたし、研修医にもそう教えてきました。 大脳皮質の高次脳機能障害を代表する症候群。 試験的には、まずそれで正しい。
ただ、現場で患者さんを診ていると、この3つは「知識として知っている」だけでは足りない、と感じる場面が何度もあります。 とくに、脳卒中と認知症。 同じ言葉が使われているのに、意味合いがまったく違う。
今日はその違いを、できるだけ臨床の言葉で整理してみます。
──
失語・失行・失認とは何か
まずは確認です。
失語とは、意識は清明で、声も出るのに、言葉の理解や表出がうまくいかなくなる状態です。 「しゃべれない」というより、「言葉として扱えない」。 質問の意味が通らない、単語が出てこない、流暢に話しているのに会話が成立しない。 こうしたズレが本質です。
失行とは、運動麻痺や感覚障害がないのに、目的ある動作ができなくなる状態です。 手は動く。 力もある。 でも、歯ブラシをどう使えばよいか分からない。 動作の設計図が壊れている、という感覚に近い。
失認とは、見える、聞こえる、触れる。 感覚入力は保たれているのに、それが何であるかを認識できない状態です。 物の形は分かるのに意味が分からない。 家族の顔が分からない。 触っても、それが何か言えない。
いずれも、麻痺や感覚障害では説明できない症状です。
──
脳卒中で出るとき
脳卒中で失語・失行・失認が出るとき、特徴ははっきりしています。
ある日、ある時から、急におかしくなる。 患者さん自身や家族が「昨日までと違う」と言う。
この場合、これらの症状は 「壊れた場所を示すサイン」 として働きます。
失語があれば、言語ネットワーク。 特定の失行があれば、頭頂葉を中心とした行為のネットワーク。 相貌失認(人の顔が見分けられない)があれば、側頭葉後部。
症状は、局在を指し示す矢印になります。
もちろん、すべてがきれいにそろうわけではありません。 失語だけ、失行だけ、ということの方が多い。 それでも、どれか1つでもあれば、皮質ネットワークの異常を疑う。 この姿勢が、診断の質を保ってくれます。
──
認知症で出るとき
一方、認知症で失語・失行・失認が出るときは、様子が違います。
いつからか分からない。 じわじわと進む。 最初は軽く、やがて重なっていく。
この場合、同じ症状名でも意味は変わります。
認知症の失語・失行・失認は 「ネットワークが静かに崩れてきた結果」 です。
どこか一か所が壊れた、というより、 複数の回路が少しずつうまくつながらなくなっていく。
だから、症状は偏らず、境界があいまいになりやすい。 失語と注意障害が混ざる。 失行と遂行機能障害が重なる。 失認なのか、見当識障害なのか、切り分けが難しくなる。
ここで大切なのは、症状名にこだわりすぎないことです。 それよりも、時間軸を見る。
急に出たのか。 前からあったのか。 最近、目立って変わったのか。
この問いが、脳卒中と認知症を分けます。
──
同じ言葉、違う役割
整理すると、こうなります。
脳卒中の失語・失行・失認は、壊れた場所を示すサイン。 認知症の失語・失行・失認は、ネットワークが静かに崩れてきた結果。
同じ言葉でも、診断学的な役割はまったく違う。
高齢だから認知症。 物忘れがあるから認知症。
そう決めてしまうと、認知症患者に起きた脳卒中を見逃します。 逆に、軽い失語だけを見て脳卒中と決めつけると、変性疾患の初期像を拾えません。
症状名ではなく、経過を見る。 この一点が、現場では何度も効いてきます。
──
前提・分析・結論
前提: 失語・失行・失認は、高次脳機能障害を代表する症状であり、脳卒中でも認知症でも出現する。
分析: 脳卒中では急性・局所的障害として、症状が局在を示す。一方、認知症では進行性・びまん性変化として、ネットワーク崩壊の結果が症状として現れる。
結論: 同じ症状名でも、時間軸と文脈で意味は変わる。症状を見る前に、経過を見る。それが診断の出発点になる。
こあら先生のひとりごと
なんだかんだ書きましたが、脳梗塞を疑った時に、大脳皮質の症状(意識障害・失語・失行・失認)があれば、アテローム血栓性脳梗塞か心原性脳塞栓症を疑います。大脳皮質の症状がない、麻痺だけの場合は、ラクナ梗塞を疑います。僕の場合、今回の知識が臨床で使われる機会ベスト1は、この瞬間です。
秘書ユナのコメント
こあら先生のひとりごとに書かれている整理は、初期対応の思考としてとても実践的です。
医学的に補足すると、この考え方は「常に当てはまる法則」ではなく、「最初に立てる仮説」として使うのが安全です。
大脳皮質症状があれば、皮質を巻き込みやすい病態、つまりアテローム血栓性脳梗塞や心原性脳塞栓症をまず考える。 一方で、皮質症状が目立たず、麻痺が主体であれば、ラクナ梗塞を念頭に置く。
この整理は、当直や救急外来での初動判断を助けます。
ただし、ラクナ梗塞でも皮質下ネットワークの障害により、軽い失語様症状が出ることがありますし、逆に皮質を巻き込む脳梗塞でも症状が乏しい場合があります。
だからこそ、この分岐は「決め打ち」ではなく、「考え始める位置」として使うのがちょうど良い。
症状の有無だけで完結させず、発症様式、時間経過、画像所見と重ねて考える。 それが、こあら先生のひとりごとを、現場で安全に活かすための前提になります。