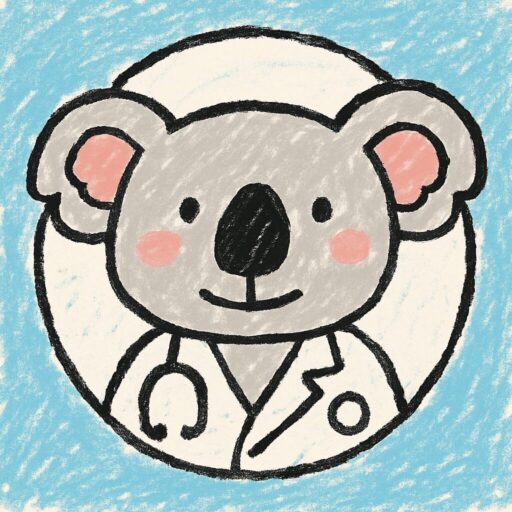脳卒中は、脳の血管に起きるトラブルの総称です。
血管が破れて血が出るものを「脳出血」、詰まって血が流れなくなるものを「脳梗塞」と呼びます。
この二つを合わせて「脳卒中」と呼びます。
くも膜下出血は脳出血の一種
脳のくも膜下腔という場所に血が出た場合は「くも膜下出血」と呼ばれます。
脳卒中の中でも、もっとも緊急性の高い病気の一つです。
原因の多くは、動脈瘤(どうみゃくりゅう)の破裂によるものです。
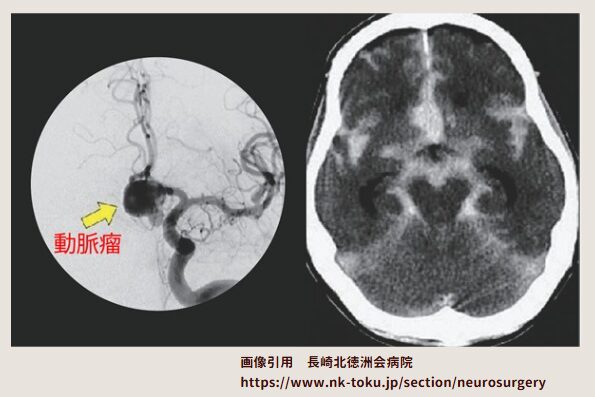
検査の前に気づける症状がある
脳卒中は「頭の中の病気」ですが、CTを撮らなくても分かることがあります。
なぜなら、典型的な症状がはっきり出るからです。
こんな症状が出ていたら、すぐに医師を呼ぶ
(1)顔の半分が麻痺している
(2)片方の腕が動きにくい
(3)片方の足が動きにくい
(4)しゃべりにくくなっている
これらが見られたら、脳卒中を強く疑います。
「いつもと違う」と感じたら、ためらわずに報告しましょう。
ACT FASTを覚えておく
厚生労働省も、一般の方向けに「ACT FAST(アクト・ファスト)」という行動指針を呼びかけています。
Face(顔):片側が下がっていないか
Arm(腕):片腕が上がらないか
Speech(言葉):ろれつが回らない、言葉が出ない
Time(時間):すぐに行動(救急要請)
医療現場で働く私たちも、日常の観察でこの4つを意識しておきたいものです。

くも膜下出血は特に危険
脳卒中の中でも、もっとも緊急処置を必要とするのが「くも膜下出血」です。
突然の激しい頭痛で発症し、「人生でいちばん痛い」と表現されることが多い病気です。
私もER当直で、何度も搬送を経験しました。
見逃せば命に関わるため、疑わしい場合はすぐCTを撮ります。
症例から学ぶ
44歳の女性。朝から何となくぼんやりし、家族に連れられて歩いて来院。
67歳の女性。夕食後から嘔吐が続き、救急車で来院。
いずれも、CTでくも膜下出血が確認されました。
「軽そうに見える」症状の中にも、重大な疾患が隠れていることがあります。
くも膜下出血は、怖い病気です。疑ったらすぐCT。これを徹底しています。
前提・分析・結論
前提:脳卒中は、脳出血と脳梗塞を含む急性疾患であり、初期対応の遅れが生命予後に直結する。
分析:FASTによる早期発見が、救命率を左右する。特にくも膜下出血は軽症に見えても危険であり、CT撮影を躊躇すべきでない。
結論:脳卒中の兆候を見逃さず、「まず疑う」「すぐ報告」「早く撮る」の3ステップを現場文化として根づかせたい。
秘書ユナのコメント
看護師さんや研修医の皆さんへ。
脳卒中は「見る力」がものを言う疾患です。
FASTの4項目を意識して日々観察するだけで、救える命があります。
報告の一言が、患者さんの未来を変えることもあるのです。
こあら先生のひとりごと
もうね、CTは、どんどん撮ったほうがいいですよ。そして頭部CT読影のコツですが、クモ膜下出血を探すことです。ダビテの星とかペンタゴンとか、その辺はもちろんですが、左右のシルビウス裂に差がないかどうか(出血してから時間が経つと白には見えませんよ)を、僕は意識して見ています。あとはね、側脳室後角の鈍化。