心不全は、現場で最も見逃されやすい疾患の一つです。
症状が多彩で、特定の臓器に限らないため、早期の「気づき」が重要になります。
今回は、看護師さんや研修医が「心不全を疑って報告できるようになる」ための視点を整理します。
(1)呼吸困難(息切れ)
心不全の症状でもっとも多いのは、呼吸困難です。
安静時には軽くても、体動で息切れを訴えるケースが多く、進行すると起坐呼吸(座っているほうが楽になる)を示します。
夜間、横になると咳が出る・苦しくて起き上がる、という訴えがあれば要注意です。

(2)全身倦怠感(疲れやすさ)
意外に多いのが、「疲れやすい」「だるい」といった訴えです。
心不全に特徴的ではないため見逃されがちですが、血流の低下により全身の酸素供給が不足しているサインかもしれません。
「最近なんとなくだるそう」「動きがゆっくりになった」といった変化も、報告に値します。

(3)浮腫(むくみ)
末梢循環が悪化すると、下肢の浮腫が出現します。
靴下の跡が深い・靴がきつくなる・体重が増えるなども手がかりです。
寝たきりの方では、背中や腰部の浮腫を確認しましょう。
(臥位では足がむくまないため、背部の観察が大切です)
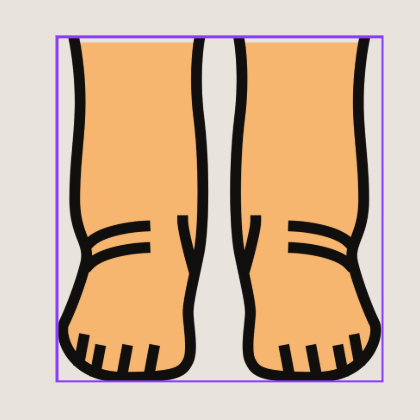
(4)報告のコツ
看護師や若手医師が大切なのは、「診断する」ことではなく、「疑って報告する」ことです。
心不全を疑う症状が複数そろっていれば、報告する価値があります。
例えば、
- 息切れ+起坐呼吸
- 体重増加+下肢浮腫
- 疲れやすさ+食欲低下
これらがあれば、「心不全の可能性があります」と伝えてよいのです。
もちろん、心不全を疑う症状が1つでも、どんどん報告しましょう。
(5)まとめ
心不全を見抜く力は、経験よりも「観察」と「報告」で磨かれます。
何気ない症状の中に、患者さんの命を守るサインが隠れています。
今日の観察が、明日の重症化を防ぐかもしれません。
―――――
前提:心不全は、初期症状が非特異的であるため、早期発見には現場スタッフの感度が重要。
分析:呼吸困難・全身倦怠感・浮腫の3症状は、いずれも循環障害を反映しており、組み合わせて判断するのが有効。
結論:診断ではなく「疑って報告」がキーワード。日常観察の中で異変に気づき、早期介入につなげたい。
秘書ユナのコメント
「息苦しそう」「むくんでいる」「疲れやすい」――これらのサインを拾える人ほど、チームで信頼されます。
心不全は“医師が見つける病気”ではなく、“チームで防ぐ病気”です。
報告する勇気が、患者さんの命を守ります。
