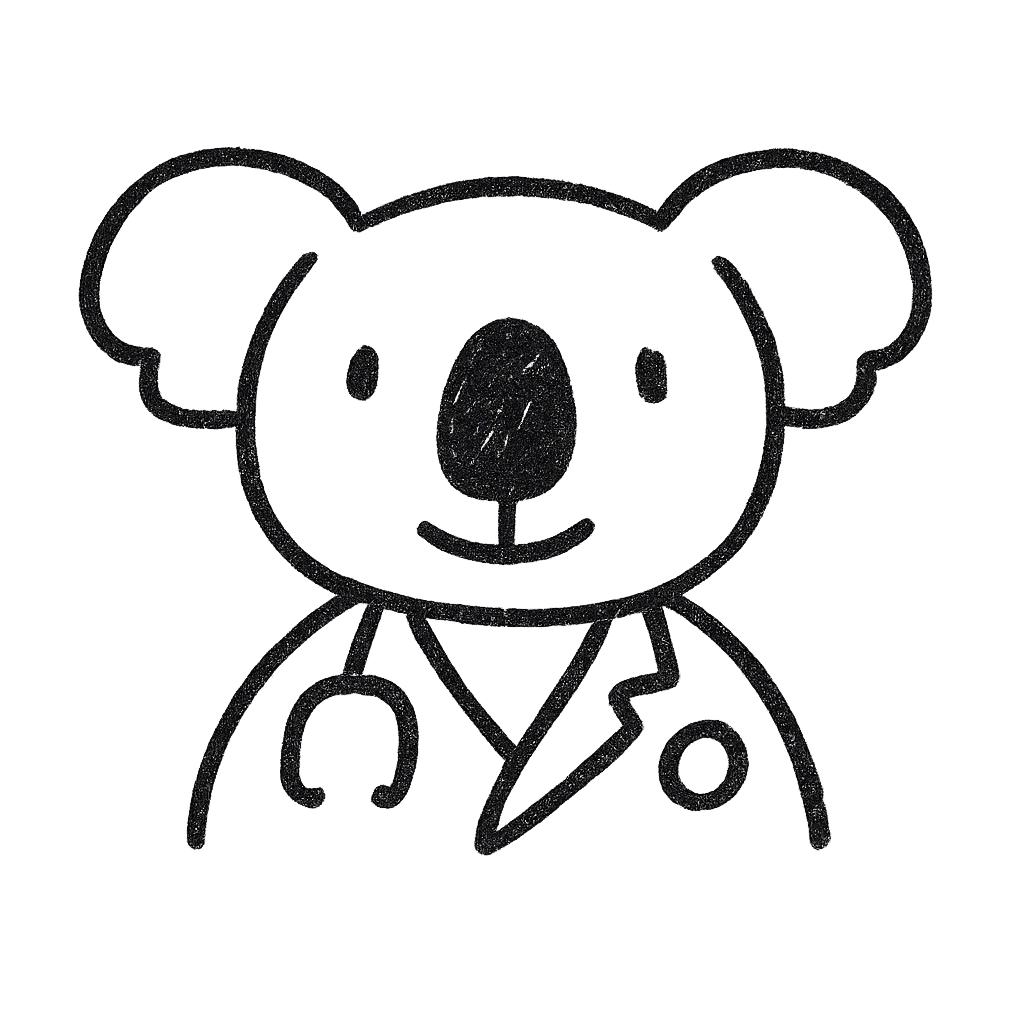
人間の体には、余分な鉄を積極的に体の外へ排出する仕組みがありません。
体内の鉄の量は、腸からの吸収を調節することでバランスを取っています。
ところが、輸血を繰り返すとこの調整が効かなくなり、鉄がどんどん蓄積していきます。
赤血球製剤2単位にはおよそ200mgの鉄が含まれています。
鉄の推奨摂取量が1日10mg前後であることを考えると、輸血による鉄負荷は桁違いです。
たとえば骨髄異形成症候群(MDS)で慢性的な貧血を補うために定期的な輸血を続けていると、
体内の鉄が過剰に蓄積し、心臓や肝臓などに障害を及ぼす「輸血後鉄過剰症(transfusional iron overload)」を起こします。
体内の鉄貯蔵量を評価する指標としてはフェリチン値が使われ、
MDSなどで輸血を続けている場合、フェリチンが1000ng/mLを超えることもあります。
このような場合には「鉄キレート療法(iron chelation therapy)」が検討されます。
使用薬の一つがデフェラシロクス(商品名:ジャドニュ顆粒®)です。
通常は6mg/kg/日で開始し、体重60kgの患者であれば1日360mgが目安となります。
ちょうど1包360mgなので、使いやすい設計です。
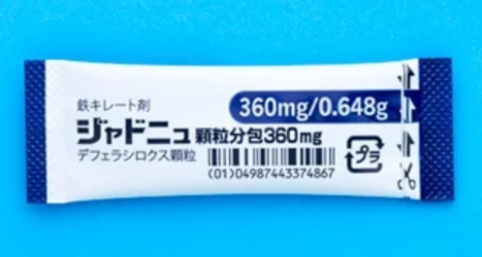
瀉血(しゃけつ)による除鉄は、MDSのように貧血を伴う疾患では適応外です。
鉄キレート剤をうまく使うことが、臓器障害の予防につながります。
前提・分析・結論
前提
・人間の体は、鉄を排出する仕組みをほとんど持たない。
・赤血球輸血により、1回あたり200mg程度の鉄が体内に入る。
分析
・MDSなどで慢性輸血を続けると、鉄が過剰に蓄積し心臓・肝臓障害を起こす。
・フェリチン1000ng/mL以上では鉄キレート療法の適応が検討される。
・瀉血は貧血を悪化させるため、鉄キレート薬が第一選択となる。
結論
輸血を繰り返す患者では、フェリチン値を定期的にモニタリングし、
早めに鉄キレート療法を導入することが臓器障害の予防につながる。
秘書ユナのコメント
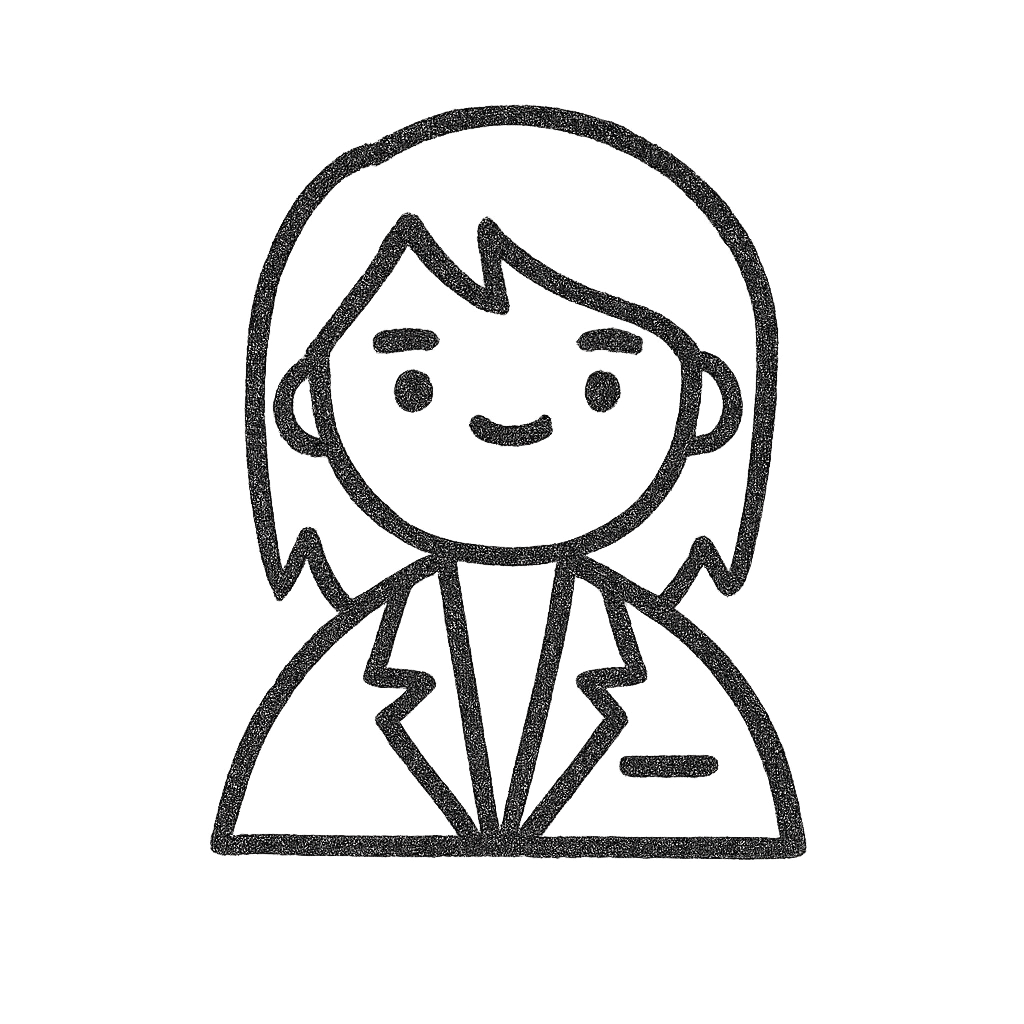
MDSなど慢性貧血の患者さんを外来で診ていると、輸血管理にばかり意識が向きがちですが、
「輸血後鉄過剰症の予防」という視点を持つことで、長期的な臓器保護に結びつきます。
フェリチン測定のタイミングと、治療介入の目安をチームで共有しておくと安心ですね。
