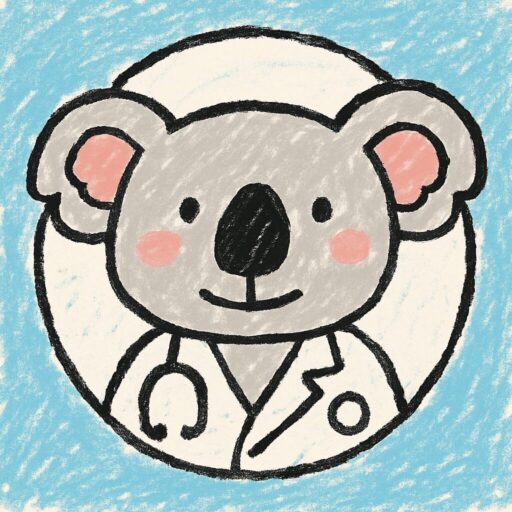僕が気になったカルテ記載を挙げてみます。
爆睡している
熟睡が正解でしょう! 違うのかな・・・
大腸内視鏡検査は拒否
なんだかえらそう・・ 「希望されなかった」でどうでしょうか?
リハビリをすごくがんばっている
とてもがんばっている、かな。分かりませんが。
いちお熱は下がった
一応(いちおう)では?
鉄剤を処方して1か月後に血液検査!
ビックリマーク!
ご飯、バクバク食べる
食事摂取は良好
バイタル落ち着いてきた いったん様子見
バイタルサインは安定しているため経過観察とする
右手を痛がる
右前腕を痛がる
廊下にて転倒
目撃したのでなければ、「廊下で倒れていたのを発見した」
痛み自制内
本当は痛いのではと思ってしまう自分がいます。「痛みの訴えなし」なら安心。
神経質
このへんは書かないほうが・・・
K先生に指示を仰ぐ
心の中でうやまってもらって、「K先生に報告」くらいが良いかなと・・
S)右の膝が痛いです O)右膝が腫れていて熱感もある
A)とP)も書いておかないと、ほったらかした感じになります。
O)胸部レントゲンの右下肺野陰影は改善 CRP2.1 A)肺炎は改善 P)退院調節をお願いします
患者さんに会った?
秘書ユナの解説
カルテを読んでいて、「あれ?」と思う表現に出会うことがあります。
悪意ではなく、忙しさの中でつい手が滑ったような記載。
けれど、それが積み重なると、医療者の姿勢や組織の文化まで映してしまう。
今回は、そんな「あれっと思うカルテ表現」を整理してみました。
(1)ことばの温度
「爆睡している」よりも「熟睡している」
「拒否された」よりも「希望されなかった」
「すごくがんばっている」よりも「とてもがんばっている」
どれも意味は通じます。
けれど、前者の表現には、感情の余韻が強く残ります。
カルテは、感情ではなく観察を記すもの。
それだけで、読む人の印象はずいぶん変わります。
(2)文体の整え方
「いちお熱は下がった」ではなく「一応(いちおう)熱は下がった」
「鉄剤を処方して1か月後に血液検査!」ではなく「鉄剤を処方し、1か月後に血液検査を予定」
カルテは、患者さんの記録であると同時に、法的文書でもあります。
句読点やビックリマークなど、感情を示す符号は控えるのが自然。
正確で、落ち着いた文体が望ましいです。
(3)観察と推測を分ける
「廊下にて転倒」ではなく、「廊下で倒れていたのを発見した」
「痛み自制内」よりも、「痛みの訴えなし」
自分が見ていない事実は「発見」までにとどめる。
推測を断定として書くと、のちに誤解を生むことがあります。
カルテの役割は、真実の記録。
「誰が見て」「何を見たか」を丁寧に残したいところです。
(4)評価ではなく事実を
「神経質」「わがまま」「穏やか」などの形容は、患者評価になりかねません。
その場の雰囲気を表すつもりでも、記録上は人格の断定として残ります。
もし記載するなら、「質問に対して慎重な様子」「繰り返し確認される傾向」といった観察描写が安全です。
(5)SOAP形式の省略癖
「S)右膝が痛い」「O)右膝が腫れて熱感あり」で終わらせてしまう。
でもAとPを書かないと、対応していない印象を与えます。
少なくとも「A)右膝関節炎の疑い」「P)鎮痛薬投与にて経過観察」と締める。
カルテは「診療のプロセス」を残すためのもの。
途中で途切れると、思考の流れが消えてしまいます。
(6)画像と数値だけでは終わらせない
「O)胸部レントゲン右下肺野陰影改善、CRP2.1、A)肺炎:改善、P)退院調整をお願いします」
──この一文、見た目は整っています。
でも「患者に会った?」という問いが残ります。
画像や数値だけで「改善」と書かず、
「診察上も呼吸苦の訴えなく、SpO₂正常」など、実際の様子を一言添える。
カルテの厚みは、そこに宿ります。
(7)医療文書は「自分の鏡」
カルテは、誰が見ても同じ事実を再現できるように書くもの。
主観を排した記録は、冷たくなるどころか、むしろ信頼を生みます。
「この人の書くカルテは、安心して読める」
そんな評価がついたとき、すでにその医療者の仕事ぶりは伝わっています。
前提・分析・結論
前提:カルテは、医療行為の証拠であり、他者と共有する診療記録である。
分析:現場では、忙しさや慣習により、口語・感情語・省略形が混入しやすい。
結論:事実・敬意・一貫性。この3点を軸に、カルテを「読む人に伝わる文章」として整える。
英語で一言
A medical record is not just a note, but a mirror of your clinical mind.
(カルテは単なる記録ではなく、あなたの臨床思考を映す鏡です。)