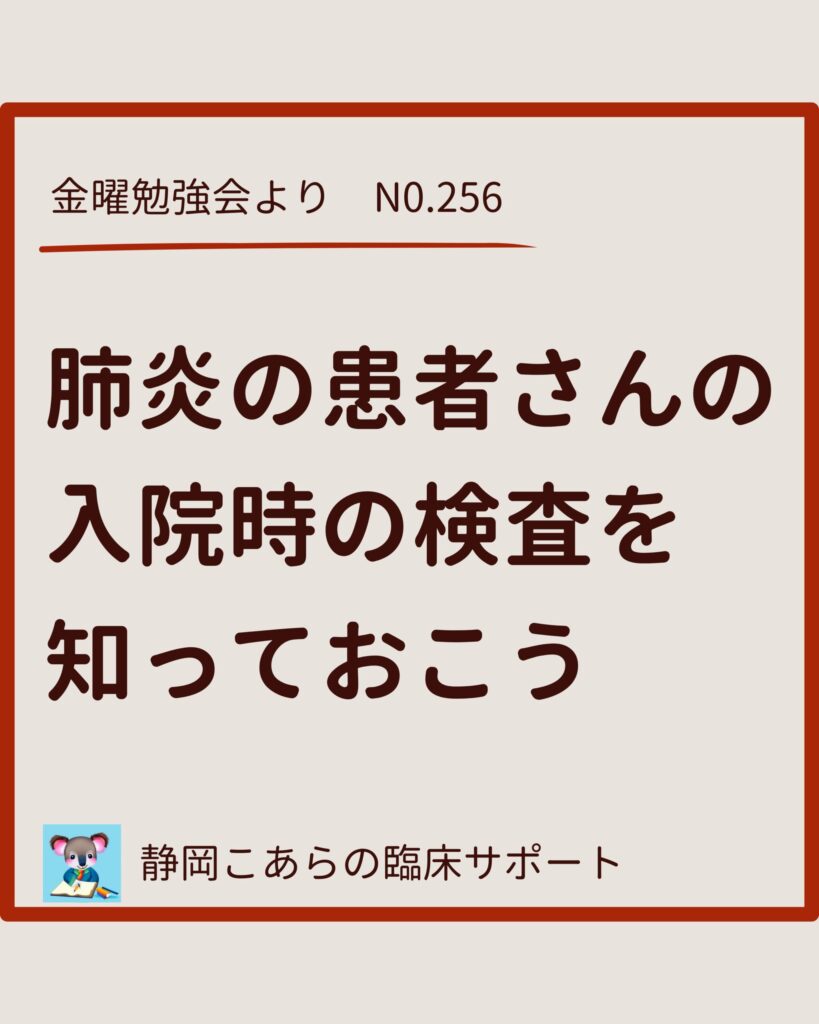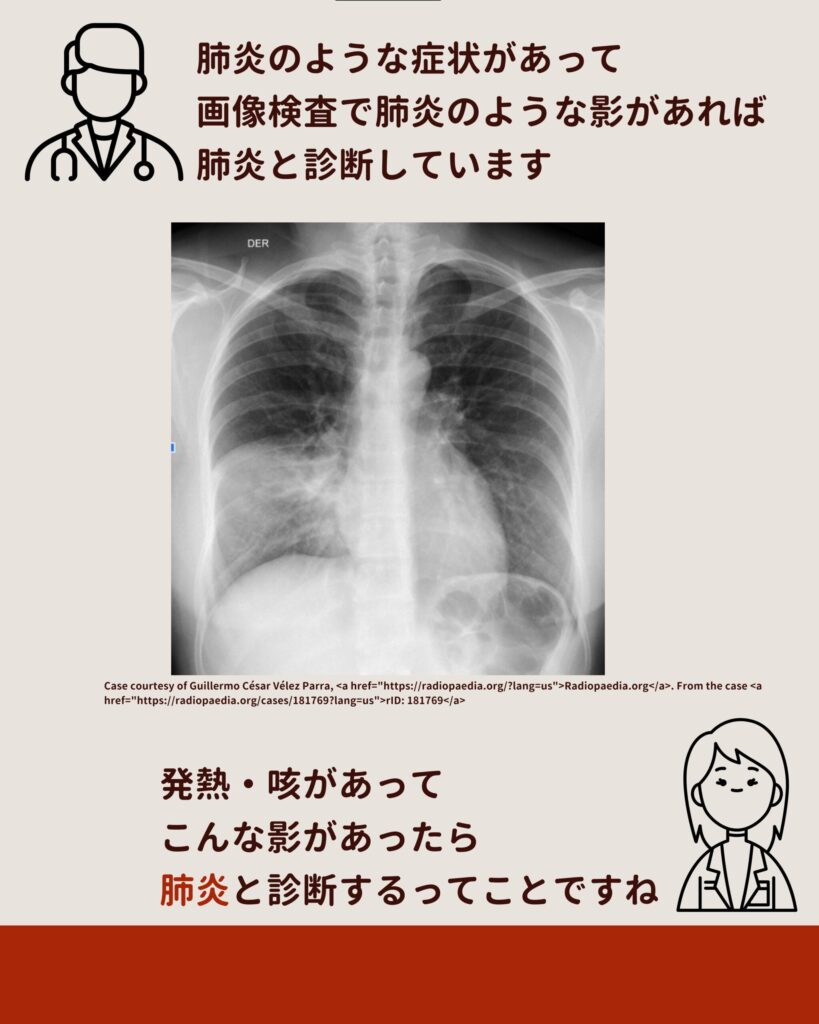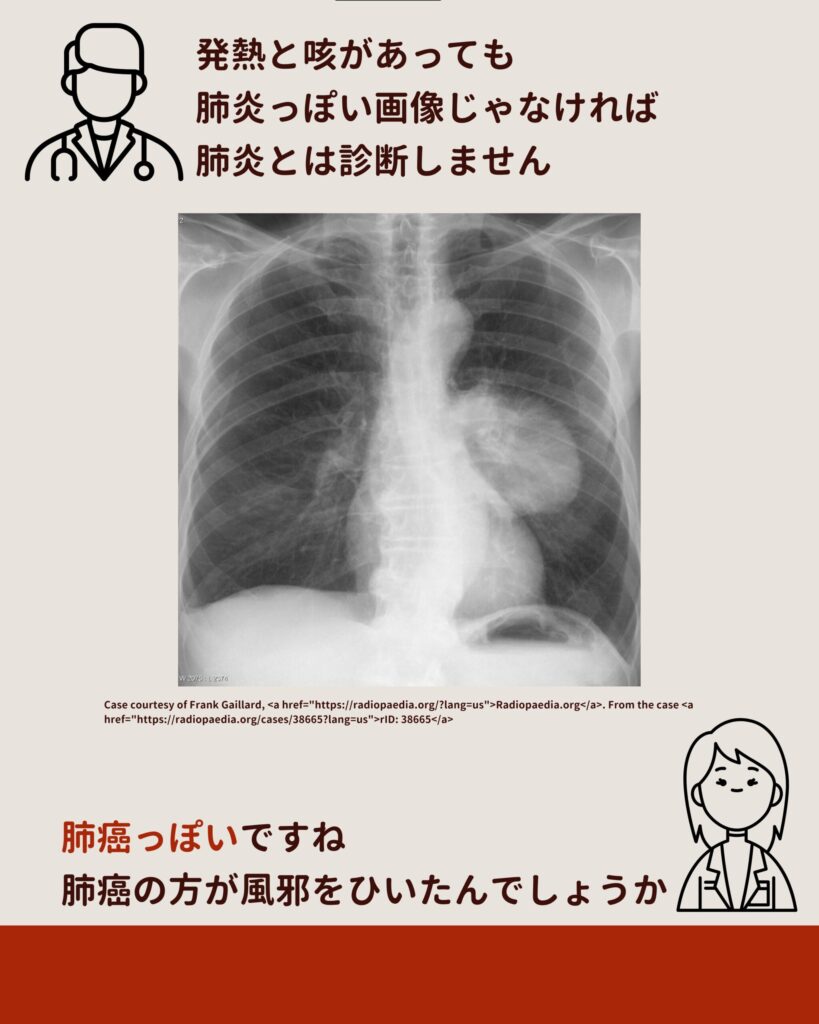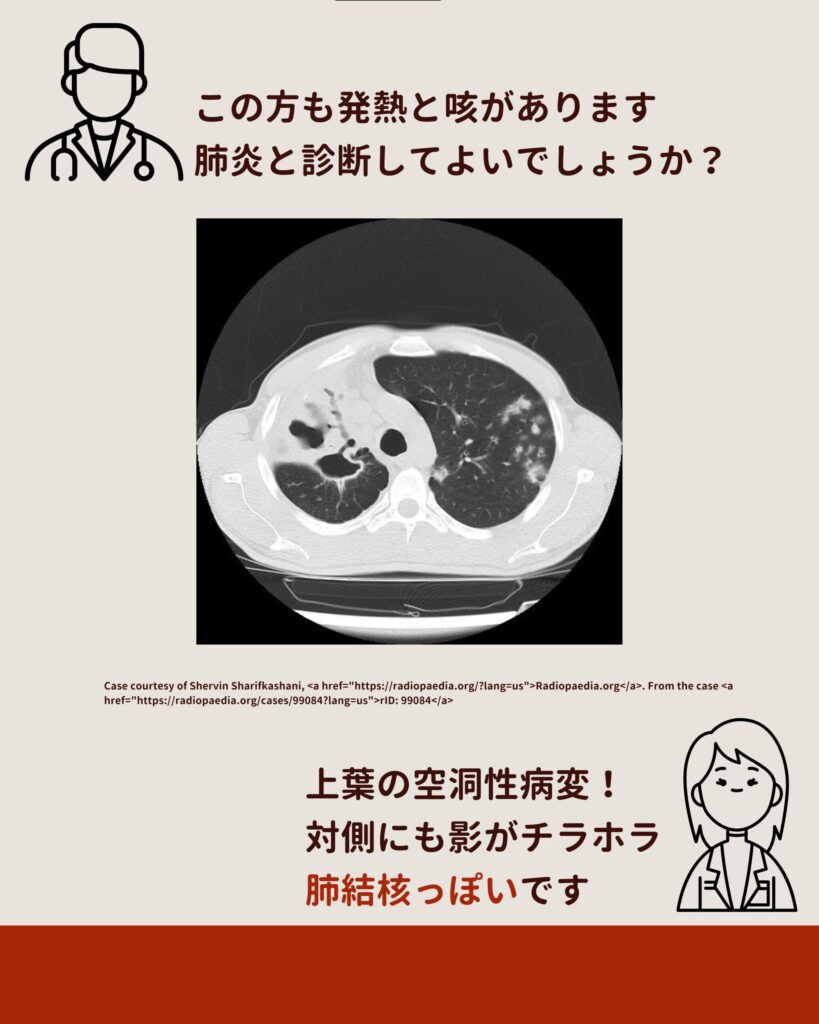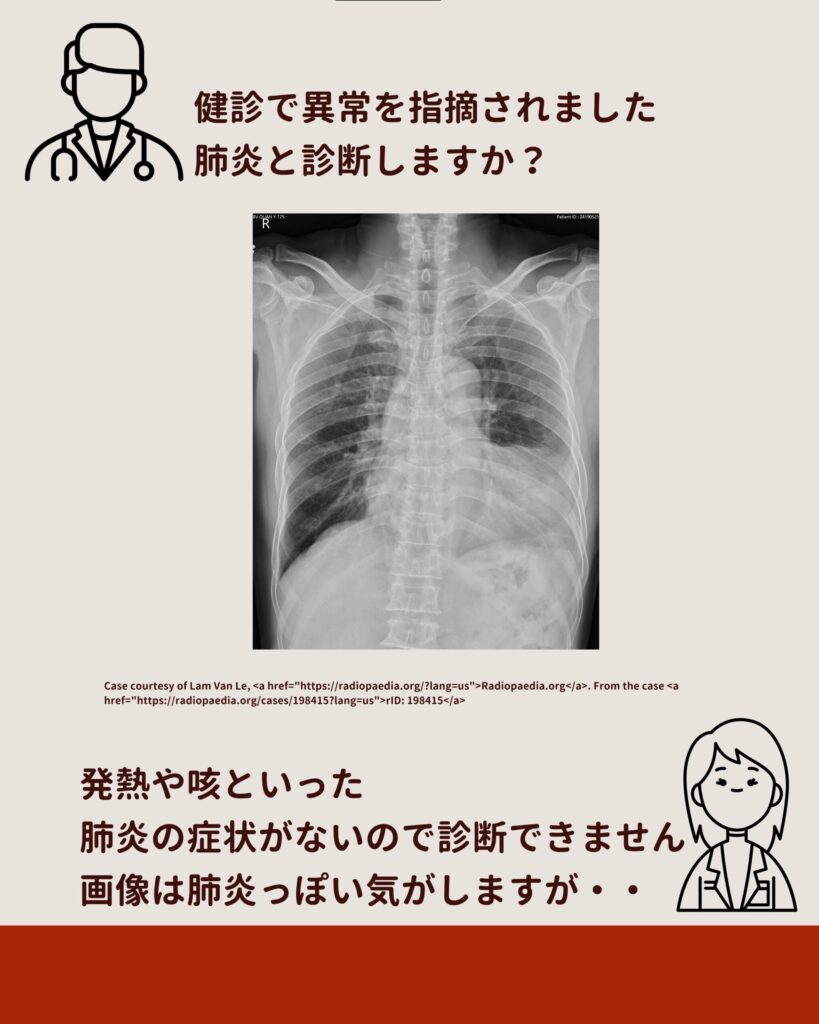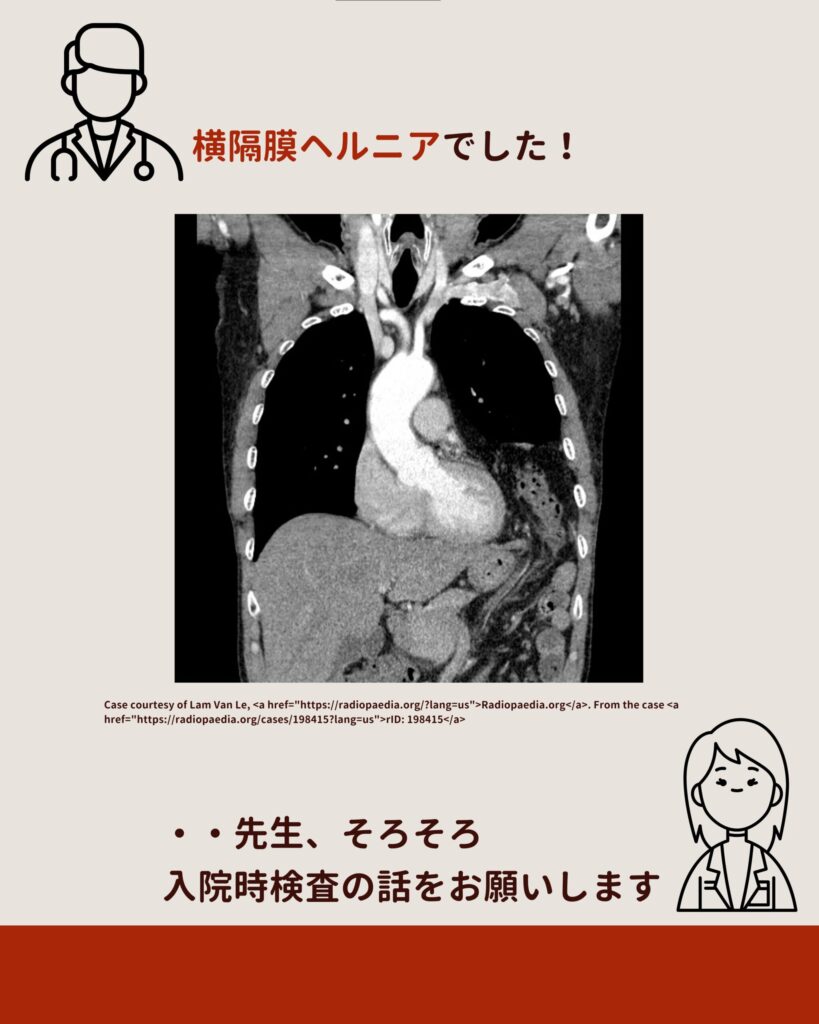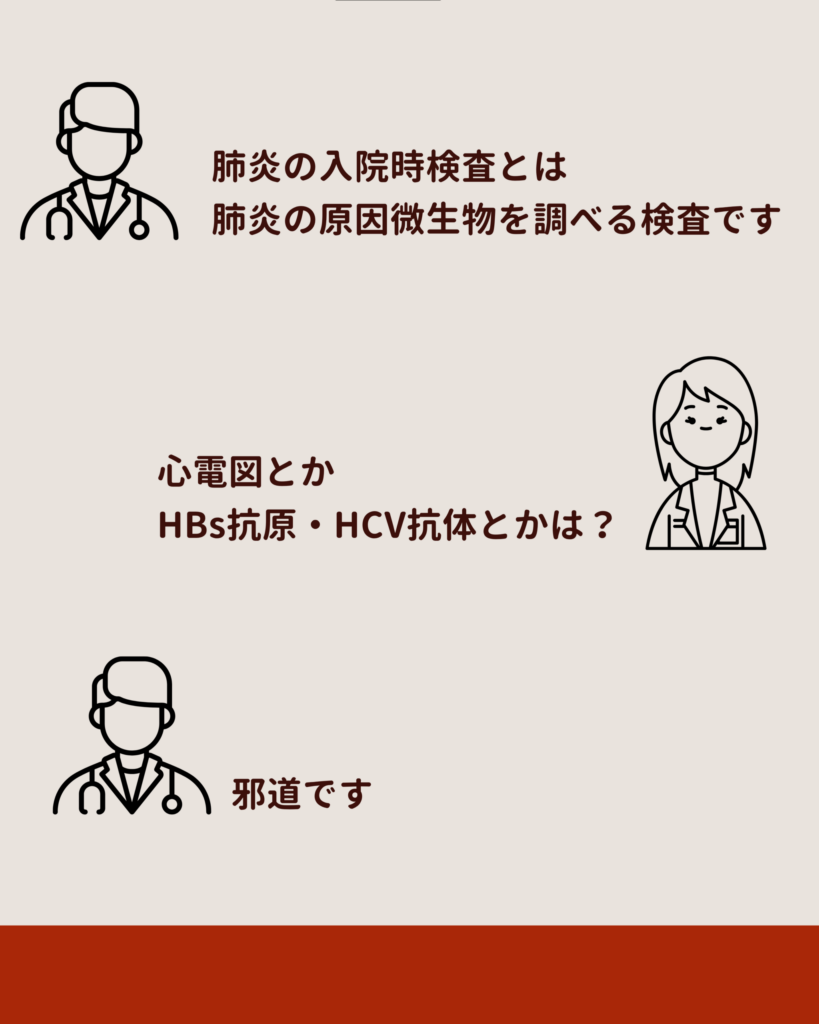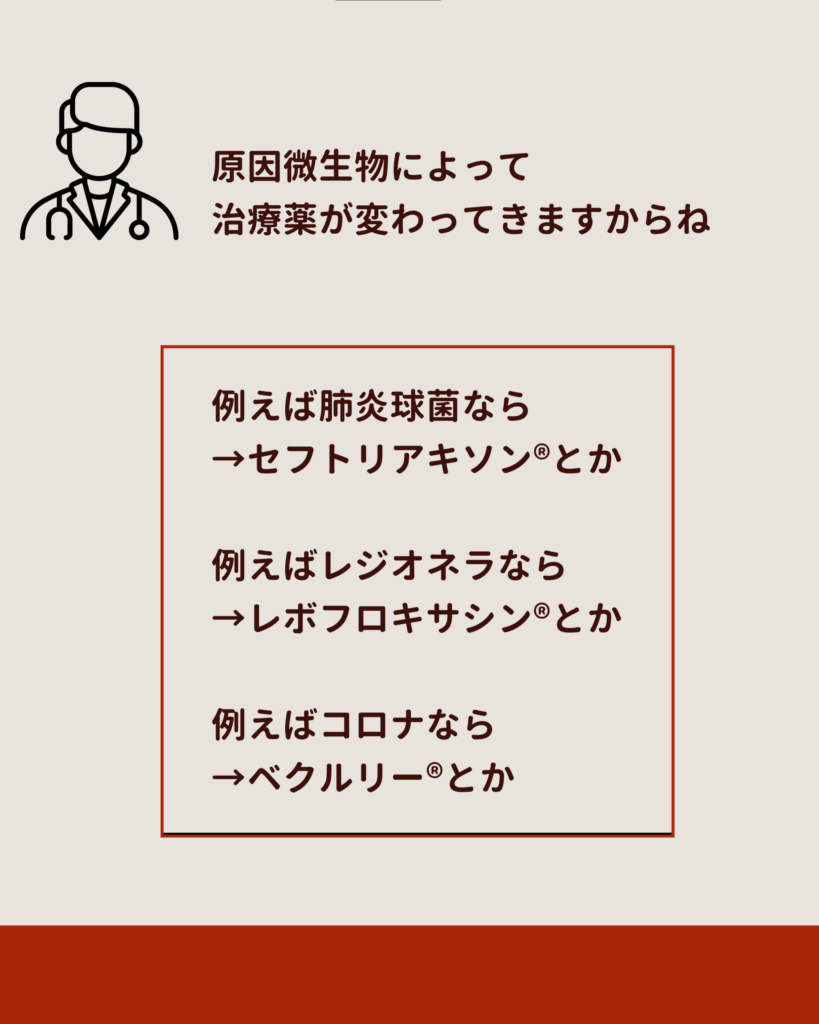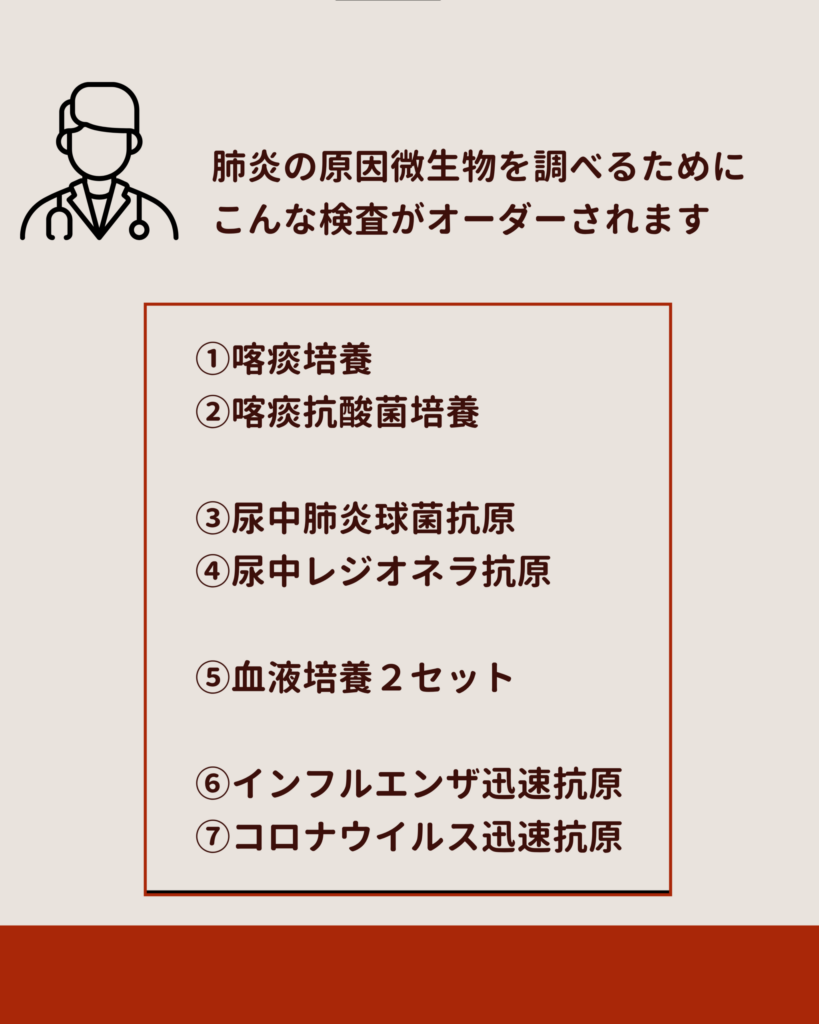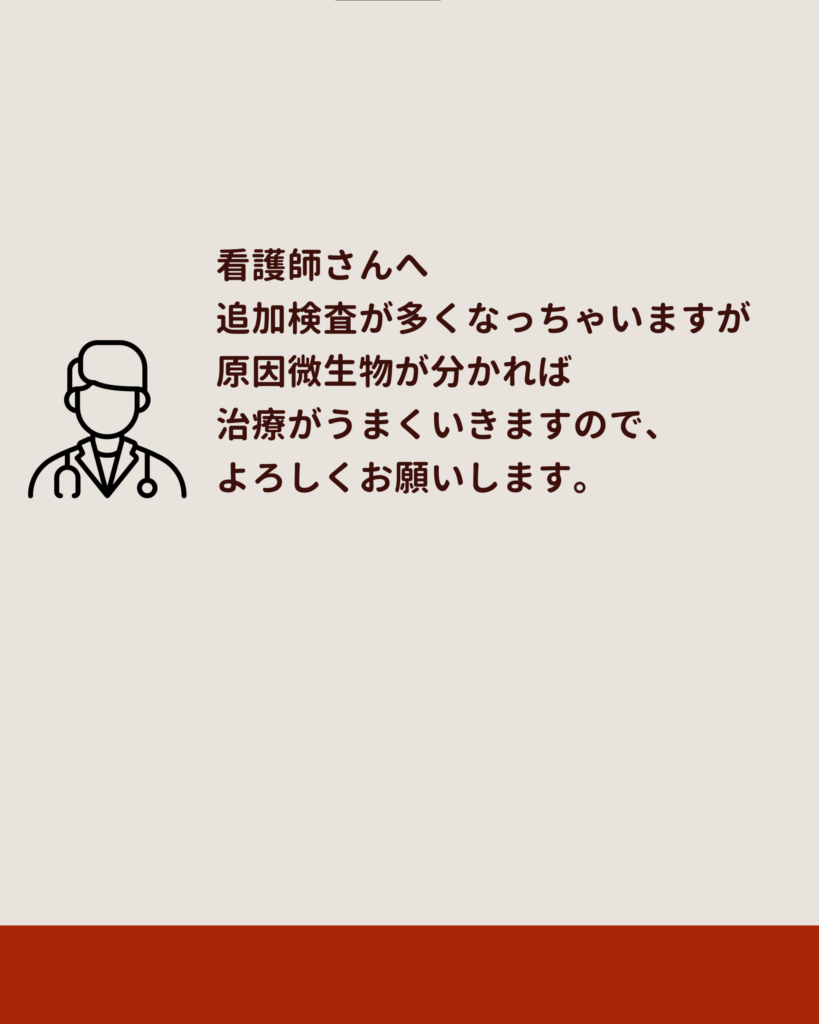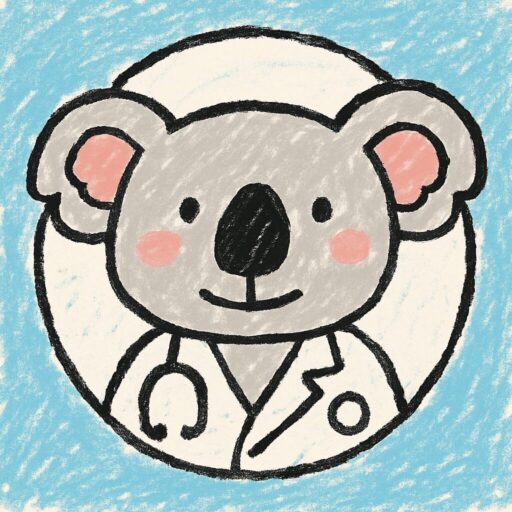肺炎のような症状があって、画像検査で肺炎のような影があれば「肺炎」と診断します。
発熱・咳があり、胸部レントゲンで浸潤影を認めれば、まずは肺炎を疑うのが自然です。
ただし――
似たような症状でも、画像が肺炎っぽくない場合は、他の疾患を考える必要があります。
たとえば肺癌、肺結核、横隔膜ヘルニアなど。
肺炎を疑ったときにまず行うべきは、「本当に肺炎なのか」を画像で確認することです。
肺炎の診断に必要な要素
(1)発熱・咳・痰・呼吸困難などの症状
(2)画像検査(レントゲン・CT)での肺炎様陰影
この二つが揃ってはじめて、臨床的に「肺炎」と診断できます。
では、入院時の検査は何をするのか?
肺炎の入院時検査とは、原因微生物(pathogen)を調べる検査です。
原因菌がわかれば、抗菌薬の選択がぐっと正確になります。
原因微生物によって治療薬は変わる
・肺炎球菌なら → セフトリアキソン®
・レジオネラなら → レボフロキサシン®
・コロナなら → ベクルリー®
したがって、どの病原体が関与しているかを早めに特定することが大切です。
入院時にオーダーされる検査一覧
(1)喀痰培養
(2)喀痰抗酸菌培養
(3)尿中肺炎球菌抗原
(4)尿中レジオネラ抗原
(5)血液培養2セット
(6)インフルエンザ迅速抗原
(7)コロナウイルス迅速抗原
この7つが、肺炎の原因検索として基本的なセットになります。
最後に、看護師さんへ
追加検査が多くなり、採取や運搬の手間もかかります。
けれども、原因微生物がわかれば治療はスムーズに進み、患者さんの回復も早くなります。
どうか、よろしくお願いします。
前提・分析・結論
前提
肺炎の診断は「症状+画像」で行うが、入院時には原因微生物の特定が治療の鍵となる。
分析
原因に応じて治療薬が異なるため、初期段階での適切な検査オーダーが重要。
特に喀痰・尿・血液の培養は、抗菌薬選択の根拠を与える。
結論
肺炎の入院時検査は「治療の地図を描く作業」。
医療チーム全体で検体採取や結果確認を丁寧に行うことで、最良の治療へつながる。
インスタグラムならこちら(静岡こあらの臨床サポート)