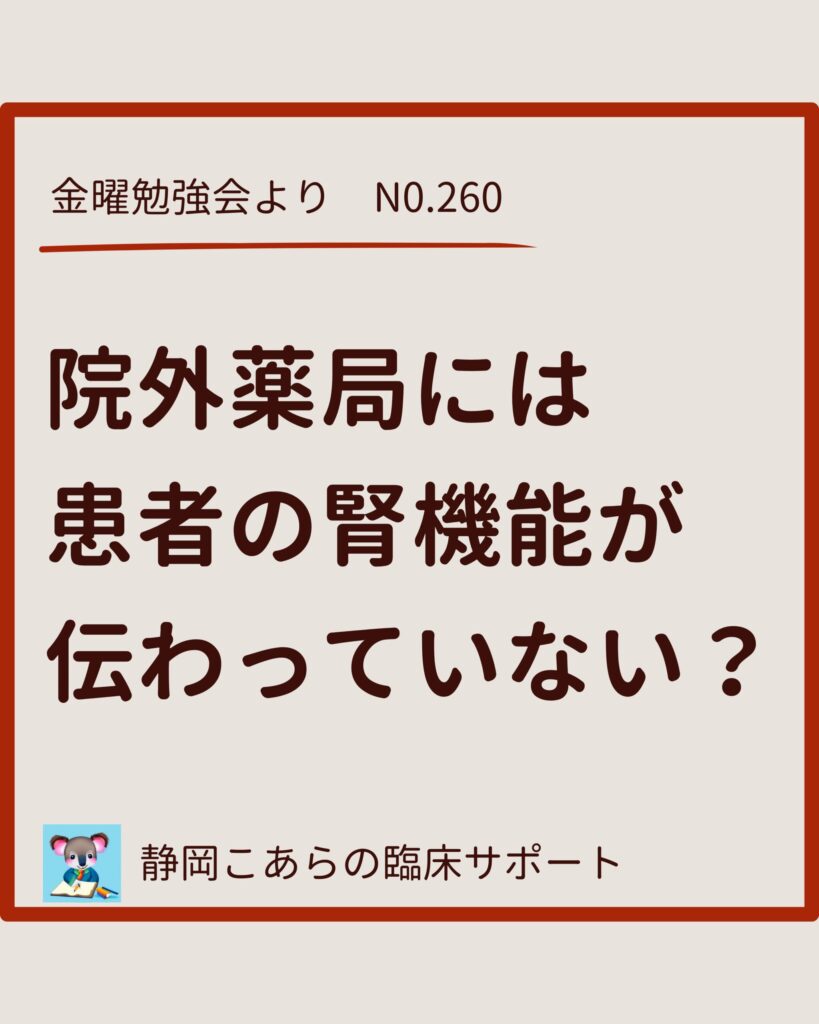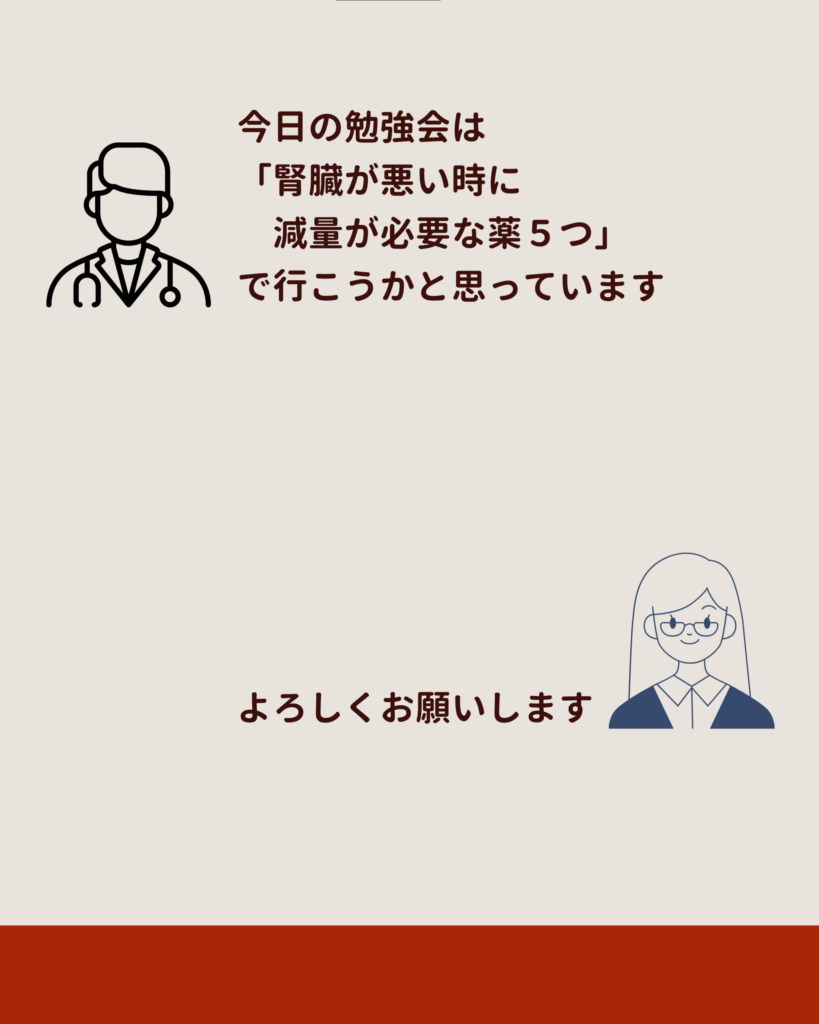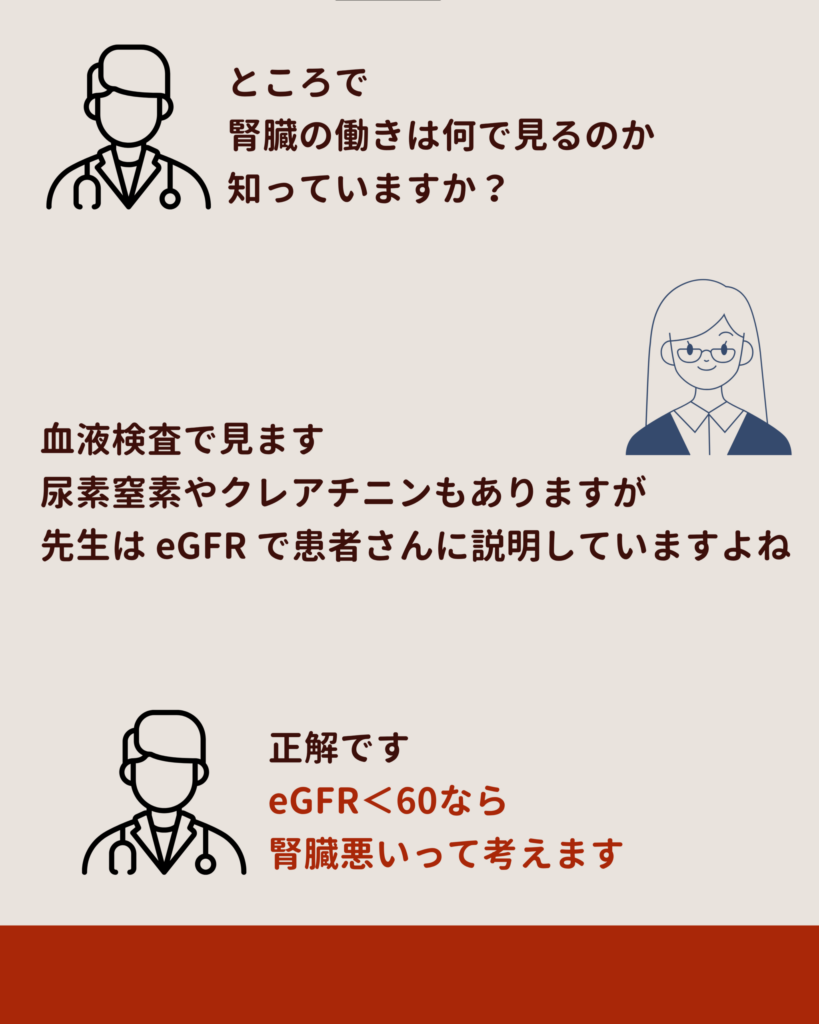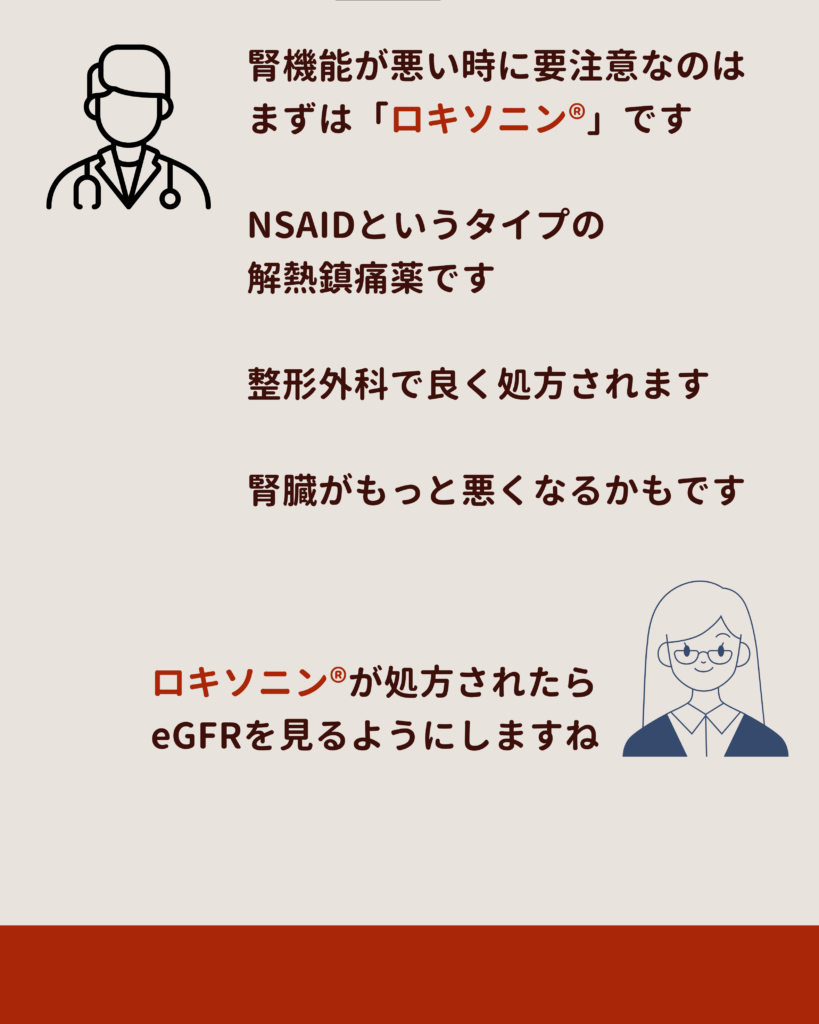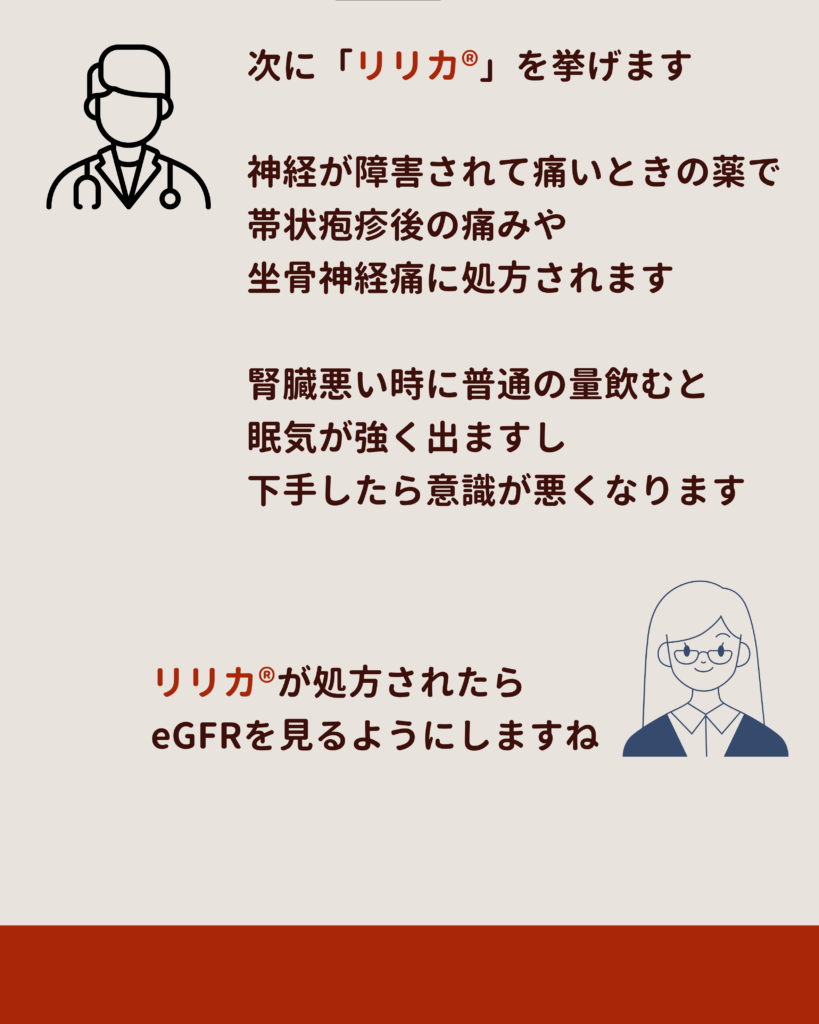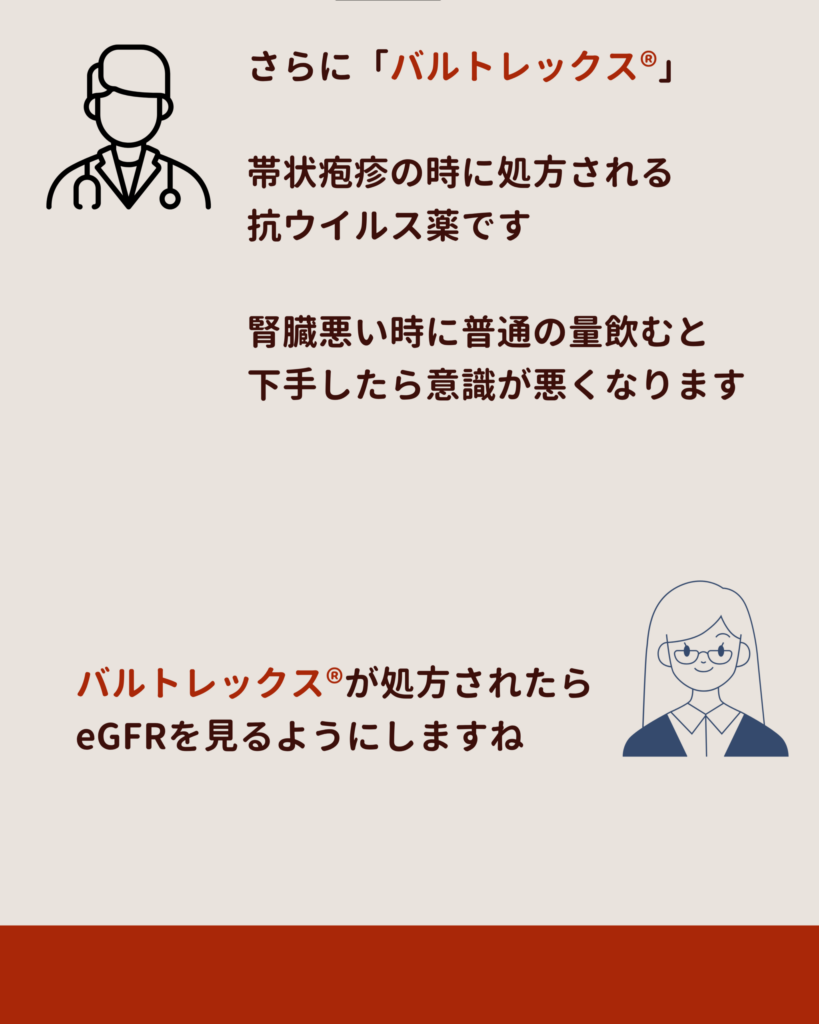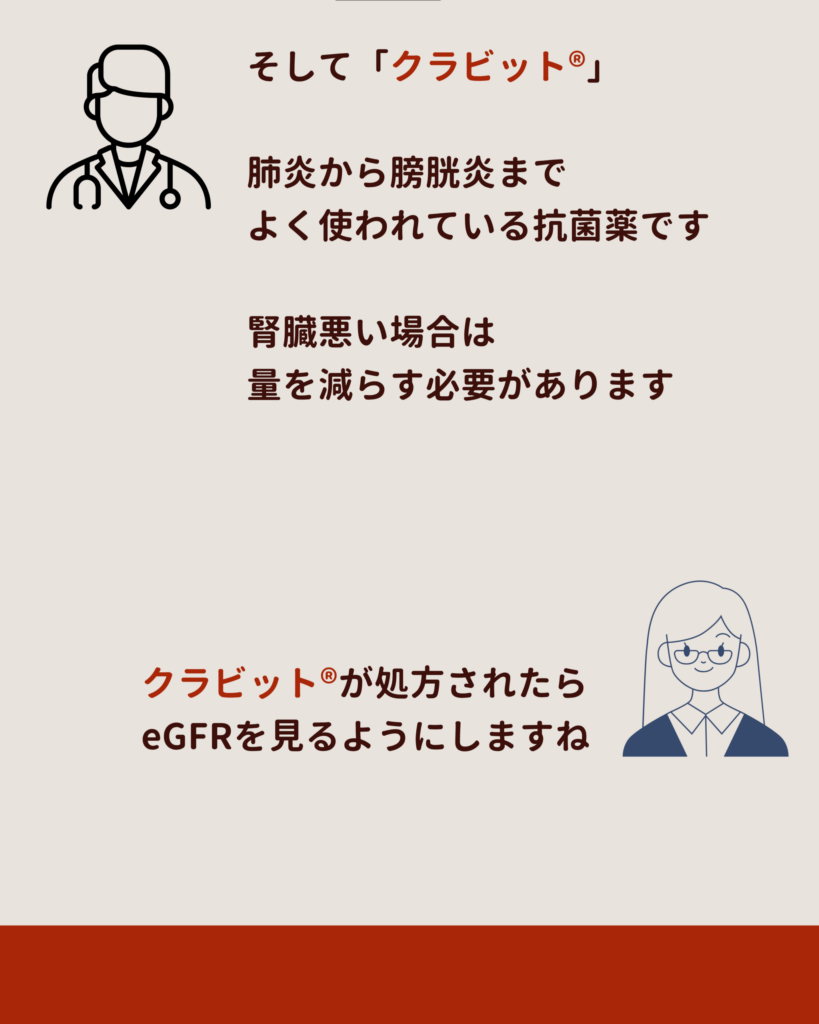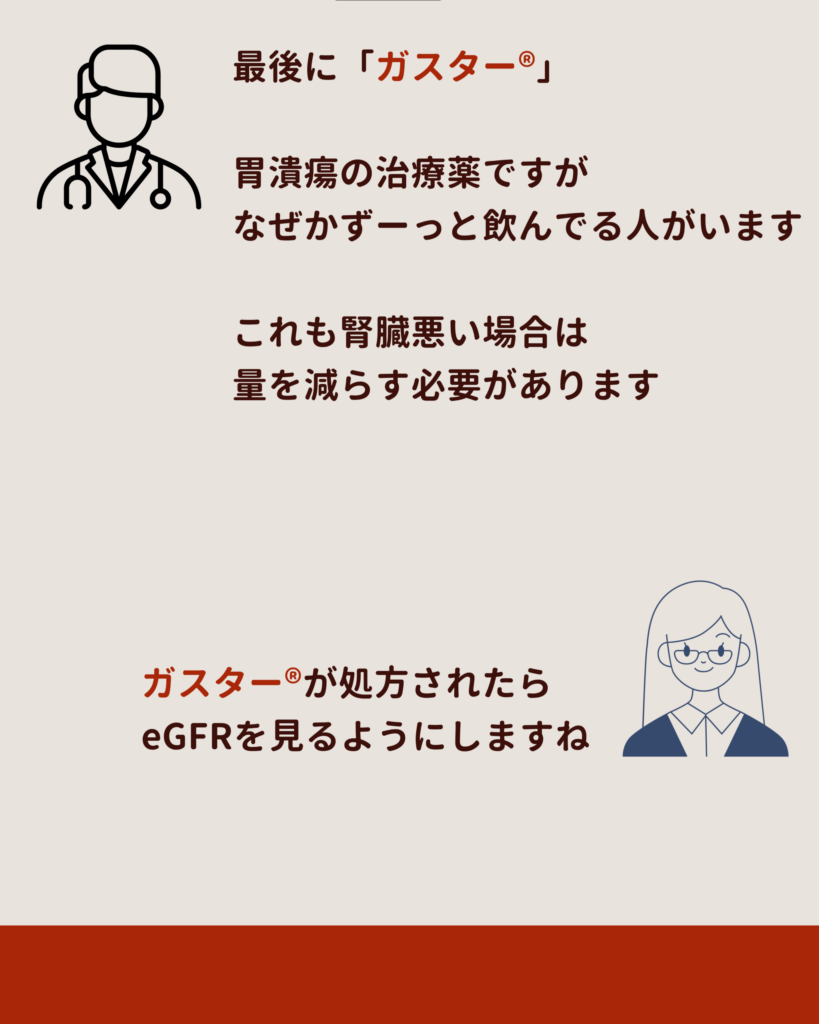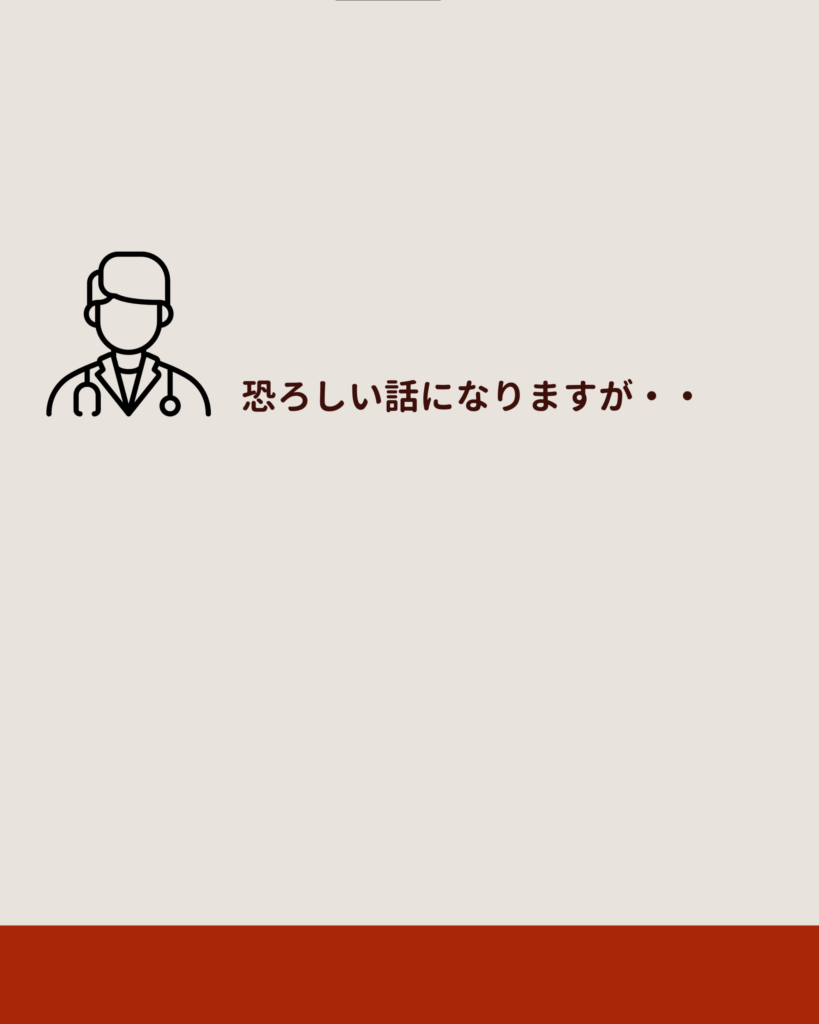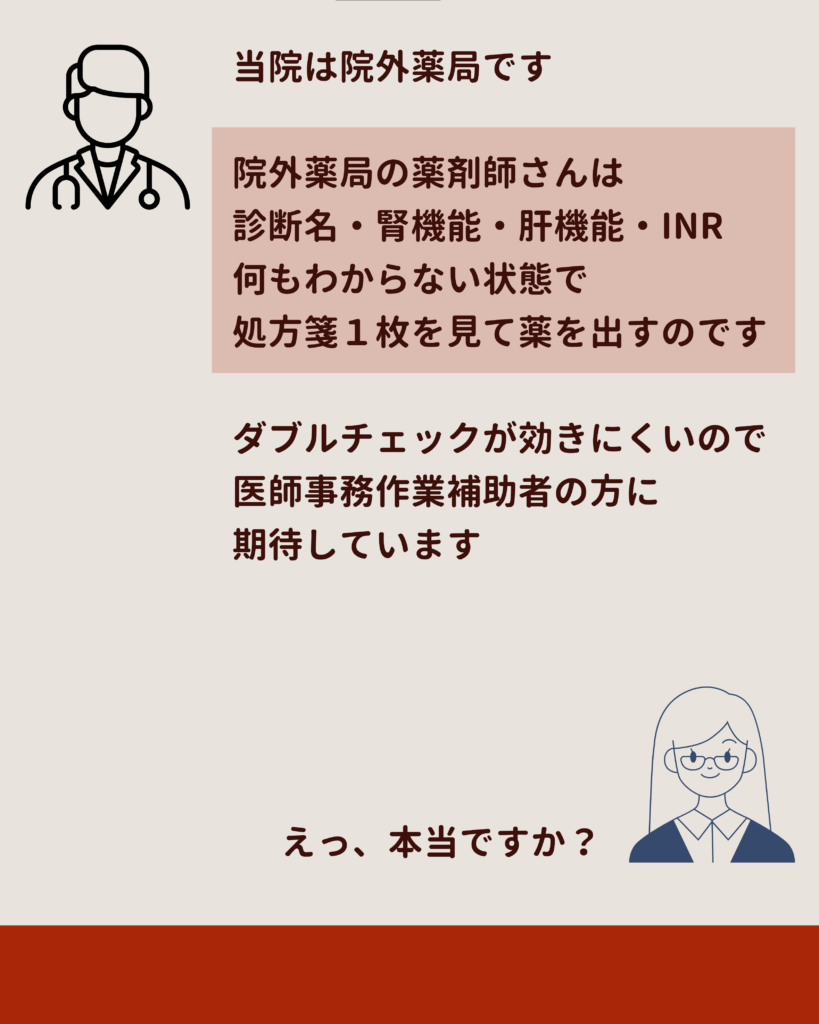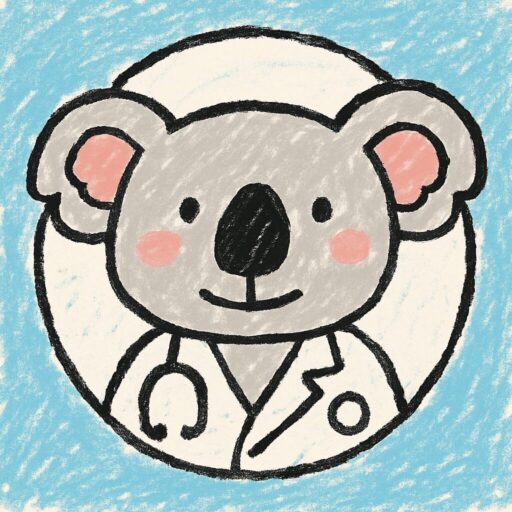導入
腎臓の働きが悪い人に、通常量の薬を出してしまう。
そんな「ヒヤリ」とする瞬間は、実は少なくありません。
今回は、腎機能が低下しているときに減量が必要な薬を5つ紹介しつつ、
院外薬局という仕組みの限界と、安全性の観点から見直すべき点を考えてみます。
(1)腎機能を見る指標は「eGFR」
腎臓の働きを表す代表的な数値が eGFR(推算糸球体濾過量)。
血液検査から計算され、60未満なら「腎機能が低下している」と判断します。
処方時にまず確認すべき項目です。
(2)腎機能低下時に注意が必要な薬5つ
(1)ロキソニン®(NSAIDs)
整形外科などでよく使われる解熱鎮痛薬。
腎血流を下げる作用があり、腎機能悪化を助長することがあります。
腎機能低下例では投与を避けるか、期間を短くするのが原則です。
(2)リリカ®(プレガバリン)
神経障害性疼痛に使われますが、腎排泄性が高く、腎機能が悪いと眠気やふらつき、意識障害を起こすことがあります。
eGFRに応じて減量が必要です。
(3)バルトレックス®(バラシクロビル)
帯状疱疹などの抗ウイルス薬。腎機能低下時には蓄積して意識障害を起こすリスクがあります。
高齢者では特に注意。
(4)クラビット®(レボフロキサシン)
肺炎や膀胱炎などで頻用される抗菌薬。
腎排泄性が強く、腎機能低下時には半量または投与間隔の延長が必要です。
(5)ガスター®(ファモチジン)
胃潰瘍治療薬として長期処方されることが多い薬。
腎機能低下例では中枢性副作用(意識障害など)が出ることがあり、減量が望まれます。
(3)院外薬局の構造的リスク
院外薬局のメリットは、
複数の医療機関を受診しても、1つの薬局で薬をまとめて受け取れる点。
また、自前の薬局を持てないクリニックや小規模病院にとって、共同利用できる仕組みでもあります。
ただし、その裏で見逃されがちなリスクがあります。
院外薬局の薬剤師は、診断名・腎機能・肝機能・INRなどの臨床情報を知らされず、
「処方箋1枚」だけをもとに調剤を行うという現実があります。
これはダブルチェックが機能しにくい構造であり、システム的な限界です。
(4)医師事務作業補助者への期待
この情報の断絶を埋めるには、
医師と薬剤師の間を支える「医師事務作業補助者(Medical Clerk)」の存在が鍵になります。
検査値を確認し、医師の意図を補足し、必要に応じて薬局に情報を伝える。
その一手間が、患者の安全を守ります。
前提・分析・結論
前提
腎機能低下時には、薬物の排泄遅延による副作用リスクが高まる。
一方、院外薬局では医療情報が共有されにくい仕組みになっている。
分析
現行制度では、腎機能などの検査値を薬局に伝える仕組みが標準化されていない。
医師事務作業補助者がその橋渡し役を担うことで、ダブルチェックが機能する可能性がある。
結論
「院外薬局のリスク」は制度の欠陥ではなく、情報の非対称性にある。
医療事務職や医師が一歩踏み込み、連携の流れを自ら設計していくことが、安全性向上の近道となる。
秘書ユナのコメント(読者へのメモ)
薬局が見ているのは「処方箋」、医師が見ているのは「検査結果」。
このズレを埋める役割は、誰が担うのか。
もしあなたが医療事務職や看護師であれば、「eGFRを確認していますか?」の一言が、患者の未来を変えるかもしれません。
インスタグラムならこちら(静岡こあらの臨床サポート)