本文(こあら先生の覚え書き)
バセドウ病、無痛性甲状腺炎、亜急性甲状腺炎。
この3つの疾患は、どれも「甲状腺ホルモンが出すぎる」ことで似た症状を示します。
ただし、原因も経過もまったく違います。
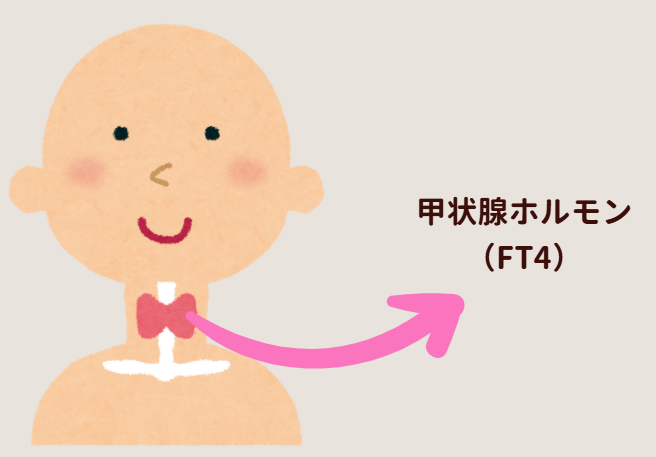
バセドウ病は、自己抗体(TSHレセプター抗体)によって甲状腺が刺激され、
ホルモンが過剰に作られてしまう病気です。代謝が上がりすぎて、
汗っかき、動悸、手の震え、体重減少などが出てきます。
心房細動を合併することもあり、注意が必要です。

一方、無痛性甲状腺炎や亜急性甲状腺炎は「作りすぎ」ではなく「漏れ出し」です。
炎症で一時的にホルモンが血中に流れ出てしまい、やがて自然におさまります。
甲状腺シンチグラフィで判別でき、バセドウ病では黒く写るのに対して、
無痛性や亜急性では取り込みが低下して白っぽく見えます。
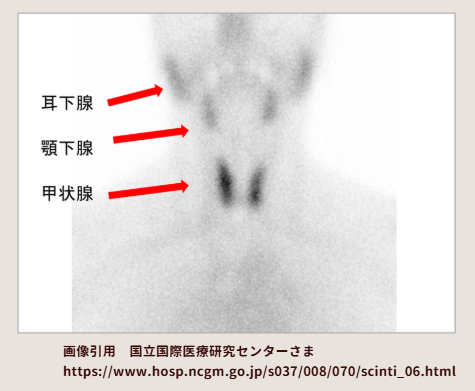
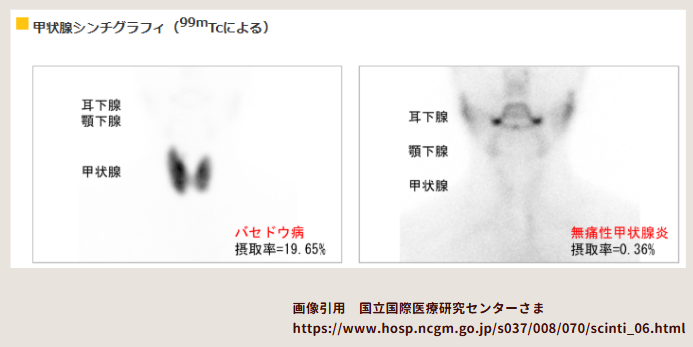
そして、診断の決め手になるのが「痛み」。
甲状腺が痛いのは亜急性甲状腺炎だけです。
ここを押さえておくと、鑑別がずいぶん楽になります。
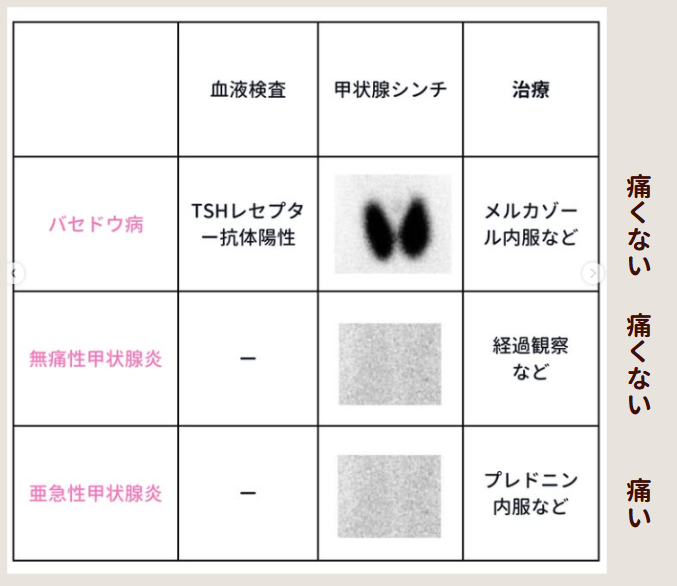
ところで、無痛性甲状腺炎って、結局何なのかという話ですが、橋本病の経過の中で、甲状腺ホルモンが漏れ出てくる時期がある、2~3ヶ月で自然におさまる。そう思ってるんだけど・・・ ちがうの?
前提・分析・結論
(前提)
甲状腺疾患は、バセドウ病・無痛性甲状腺炎・亜急性甲状腺炎が代表的。
症状だけでは区別がつきにくく、検査と経過観察が不可欠。
(分析)
ホルモンの「産生過剰」なのか「漏出」なのかを見極めることが第一歩。
加えて、「痛みの有無」「シンチの取り込み」「自己抗体の有無」を整理すると理解が深まる。
(結論)
甲状腺が「痛い」かどうか、それが診断の分かれ目です。
体調不良が続く患者を前にしたら、まずFT4を測定してみましょう。
