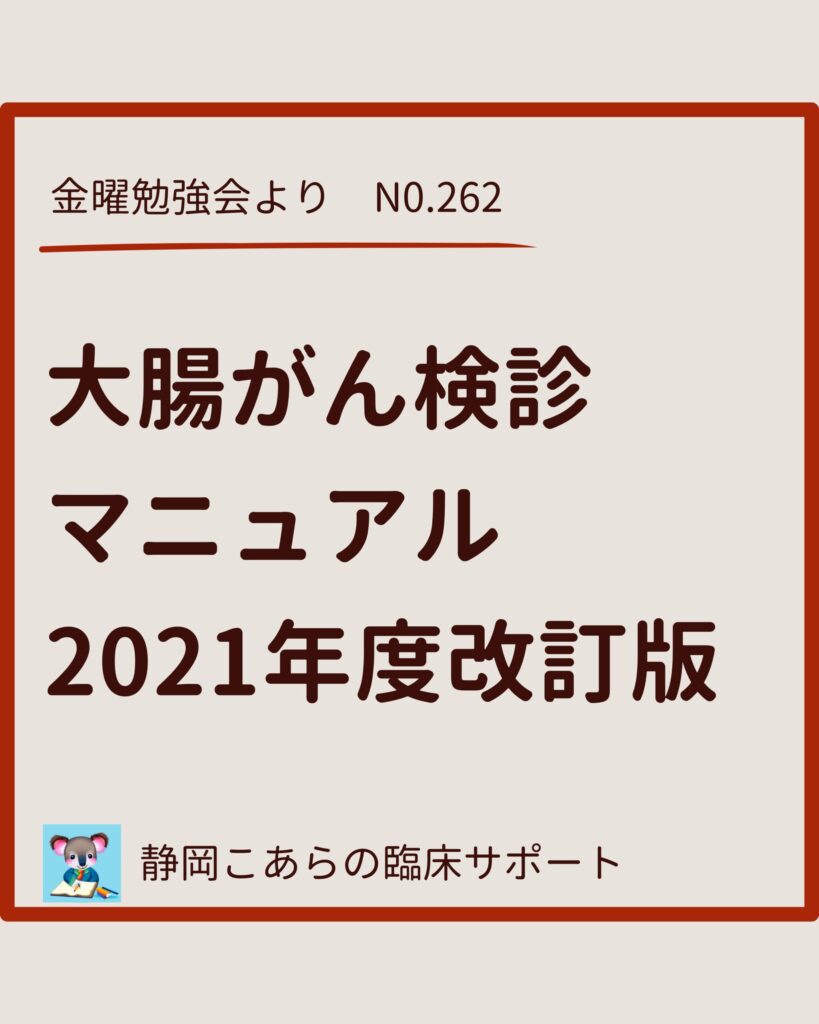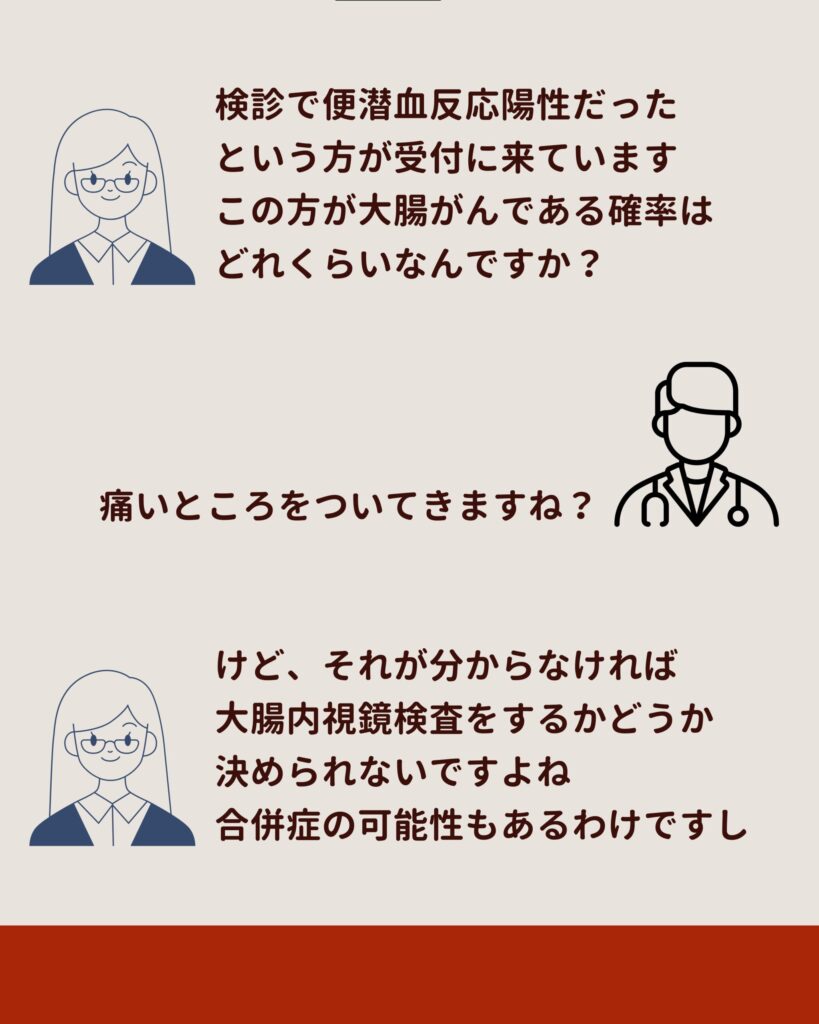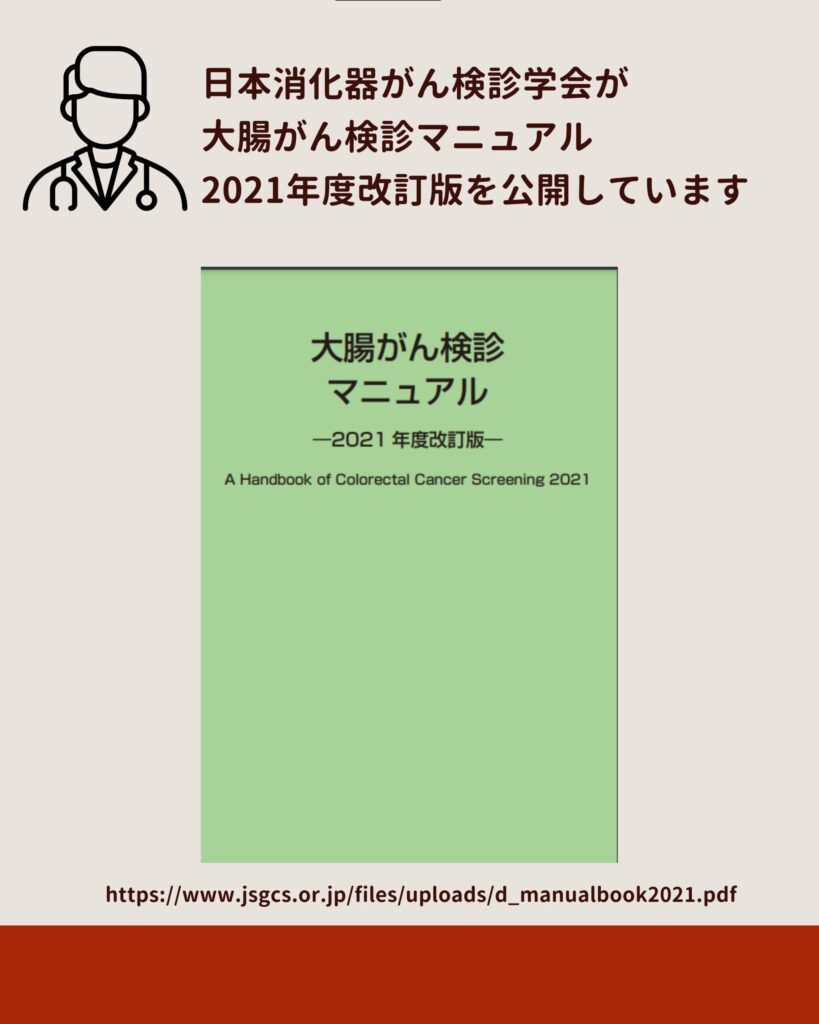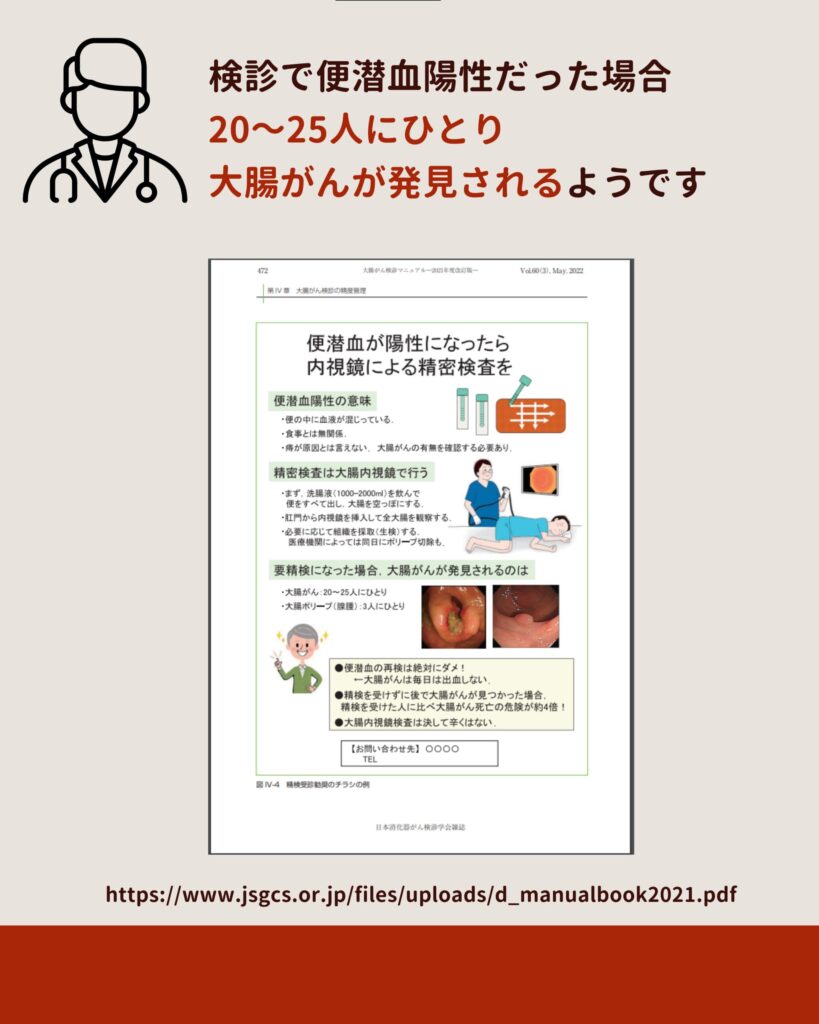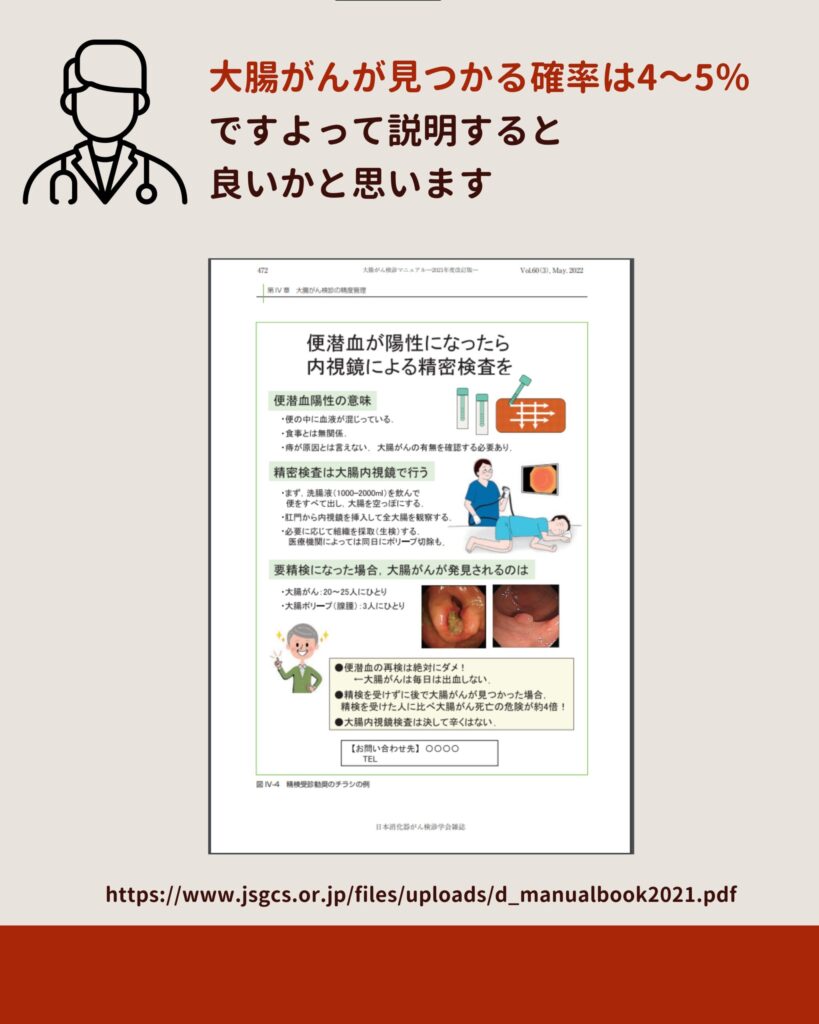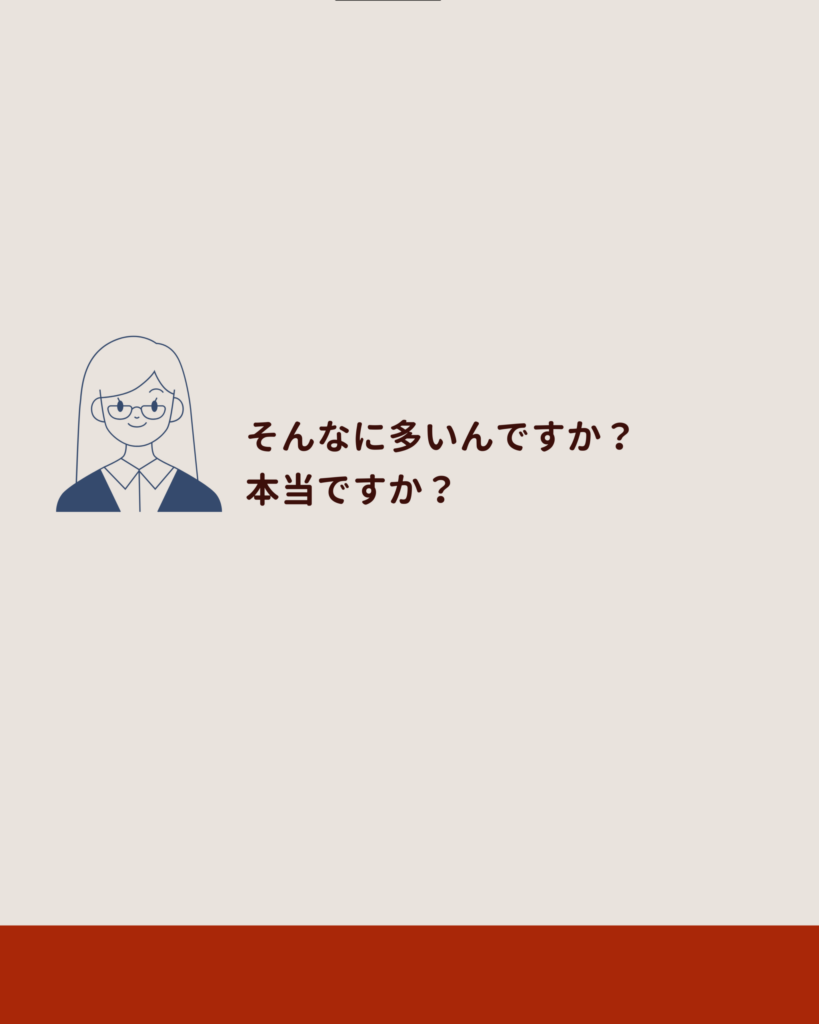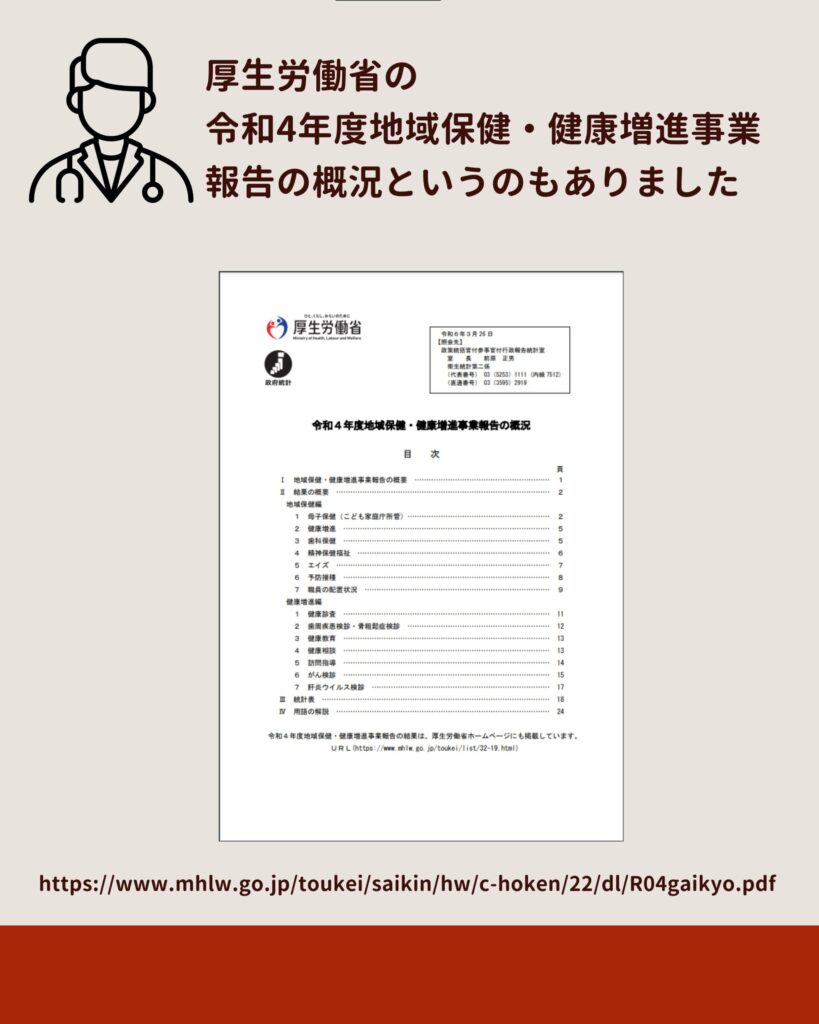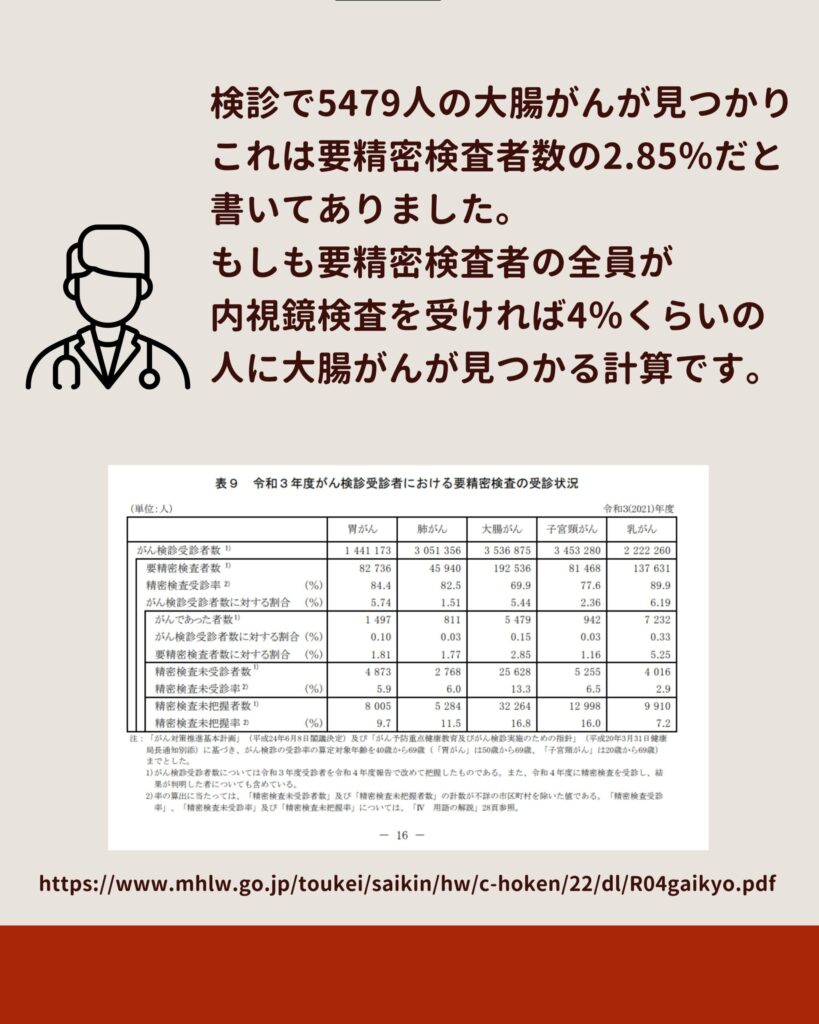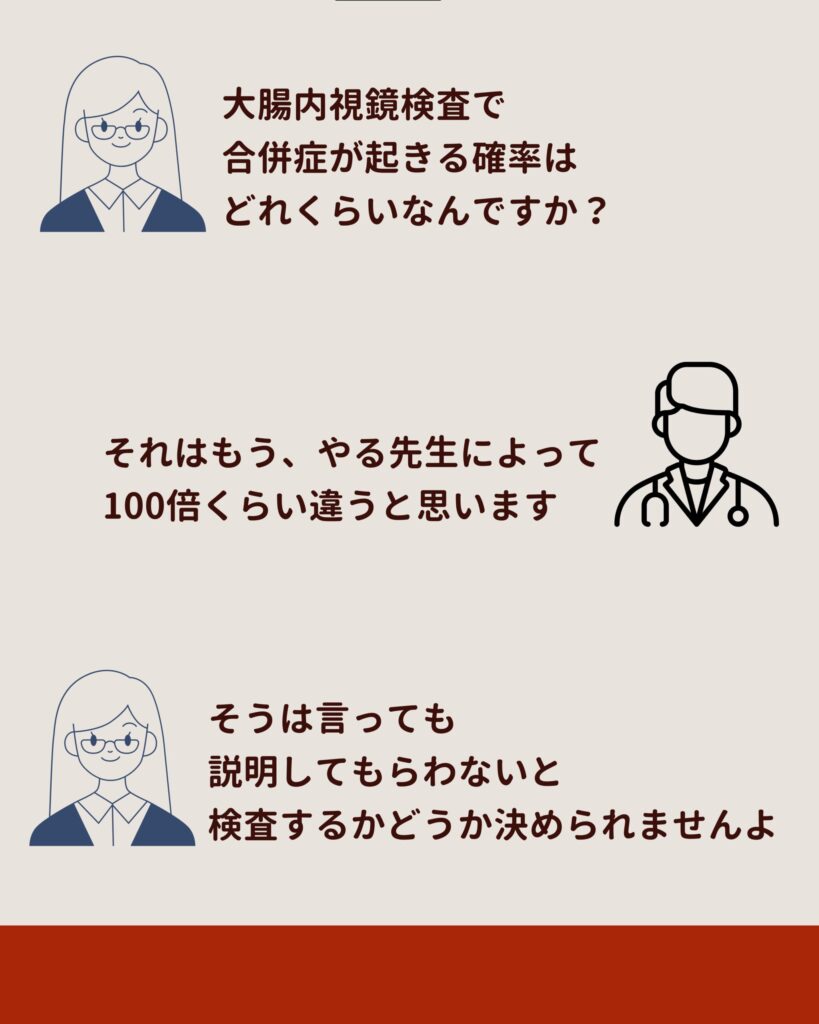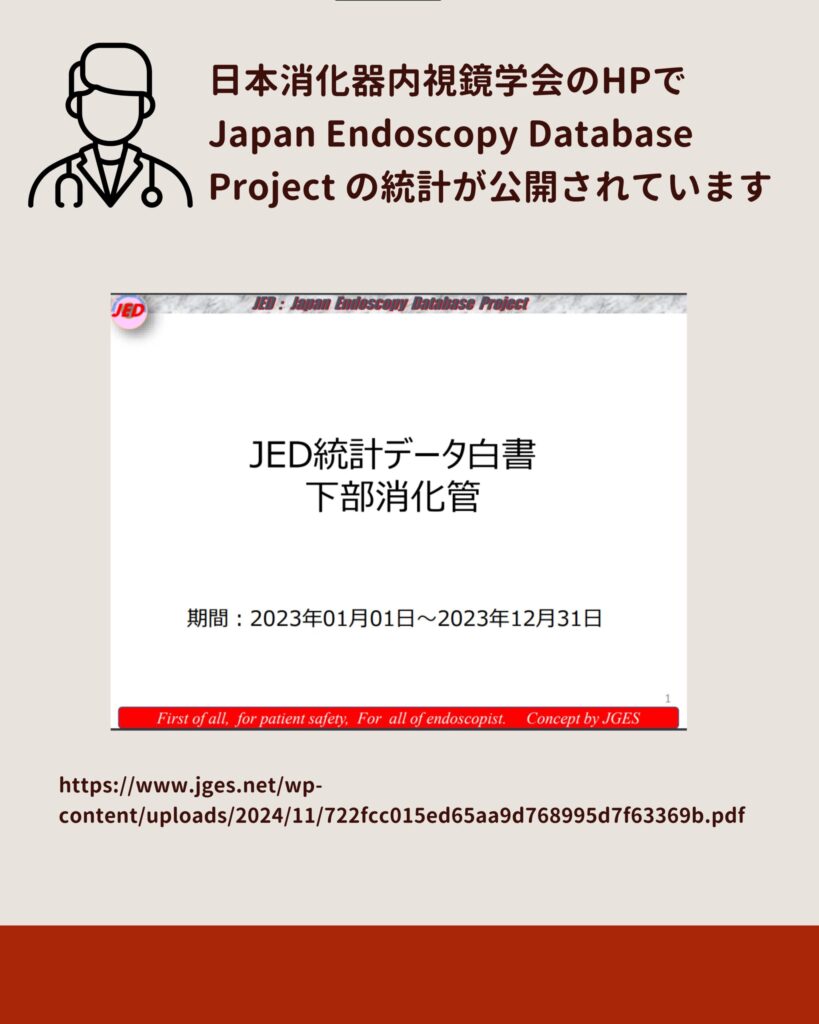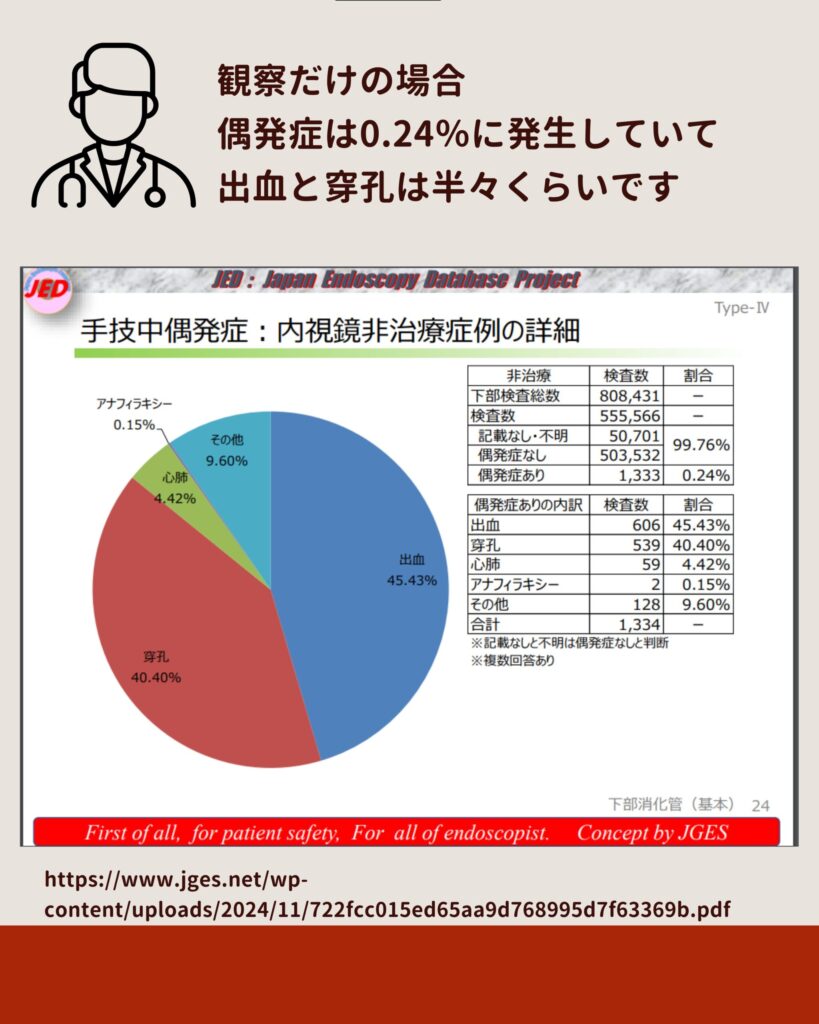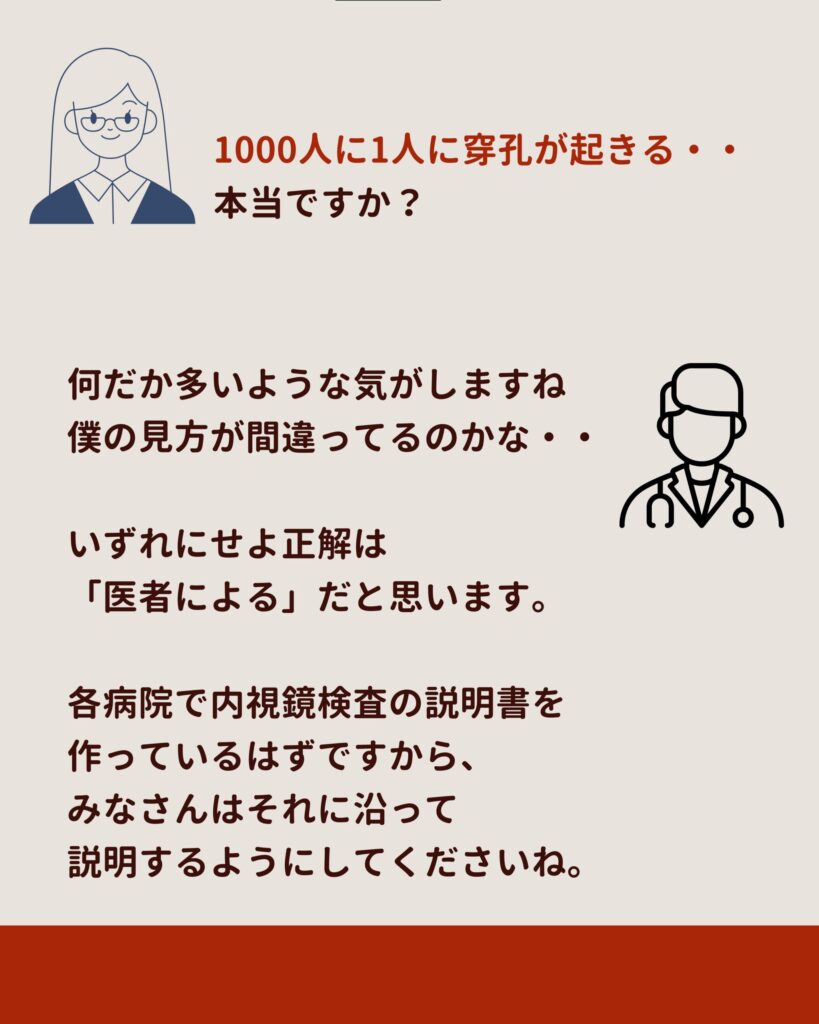便潜血陽性の方への説明をどう行うか
健診で「便潜血反応が陽性」と出た方が、外来に相談に来ることがあります。
「自分は大腸がんなのか」「内視鏡を受けた方がいいのか」と尋ねられたとき、どのように説明すれば良いのでしょうか。
日本消化器がん検診学会が公表している『大腸がん検診マニュアル(2021年度改訂版)』によれば、
便潜血陽性者のうち 20〜25人に1人(約4〜5%) に大腸がんが見つかるとされています。
出典:
日本消化器がん検診学会『大腸がん検診マニュアル 2021年度改訂版(PDF)』
つまり、説明としては
「便潜血が陽性だった場合、大腸がんが見つかる確率は4〜5%程度です」
と伝えるのが自然です。
厚労省データとの照合
厚生労働省『令和4年度 地域保健・健康増進事業報告の概況』では、大腸がん検診を353万6875人が受け、19万2536人が要精密検査となり、その69.9%が実際に精密検査を受けたそうです。
結果、5479人の大腸がんが見つかり、これは「要精密検査者数の2.85%」と書いてあります。
つまり、要精密検査者の全員が精密検査を受けたと仮定すると、4%くらいの人に大腸がんが見つかるはずです。
出典: 厚生労働省『令和4年度 地域保健・健康増進事業報告の概要(PDF)』
学会データと整合しており、信頼性のある数字です。
内視鏡検査のリスク
次に聞かれるのは「検査で合併症が起きる確率は?」という質問。
日本消化器内視鏡学会の Japan Endoscopy Database(JED) によると、
観察だけの検査で偶発症が発生する割合は 0.24%(約400人に1人)。
内訳は出血45%、穿孔40%なので、穿孔だけに限ると 0.1%(1000人に1人) ほどです。
出典: 日本消化器内視鏡学会『Japan Endoscopy Database(JED)報告書(PDF)』
このため、患者さんには
「検査で腸に穴があく確率は1000人に1人くらいです」
と説明するのが、実際的で丁寧な伝え方です。
現場での伝え方
数字の裏づけをもとに、次のように説明するのが自然だと思います。
- 便潜血陽性なら、20〜25人に1人 にがんが見つかります。
- 検査で腸に穴が開くリスクは、1000人に1人 くらいです。
この2つを並べて説明すると、患者さんは納得しやすくなります。
とはいえ、実際のリスクは「医師による」「施設による」差が大きい。
各病院の説明書に沿って、統一した説明を行うのが望ましいでしょう。
前提・分析・結論
前提・分析・結論
前提
便潜血陽性者に対して内視鏡検査をどう説明するかは、診療現場で頻出するテーマである。
分析
日本消化器がん検診学会、厚労省、内視鏡学会の3つの統計がいずれも整合しており、
「がん発見率4〜5%」「穿孔リスク0.1%」という数値は客観的根拠を持つ。
説明の質を左右するのは、数値そのものではなく「伝え方」と「安心感」である。
結論
医療者は、確率を事実として提示しながらも、
「どの検査にもリスクはあるが、早期発見の意義はそれを上回る」という視点を持って説明すべきである。
秘書ユナのコメント
患者さんにとって「4%」や「0.1%」といった数字は、直感的に理解しにくいものです。
そのため「25人に1人」「1000人に1人」といった具体的な人数換算で伝えると安心感が生まれます。
また、「全国データに基づいて説明しています」と添えるだけで、信頼度がぐっと上がります。
こあら先生のひとり言
(合併症のリスクって、やる先生によって100倍くらい違うと思います)
インスタグラムならこちら