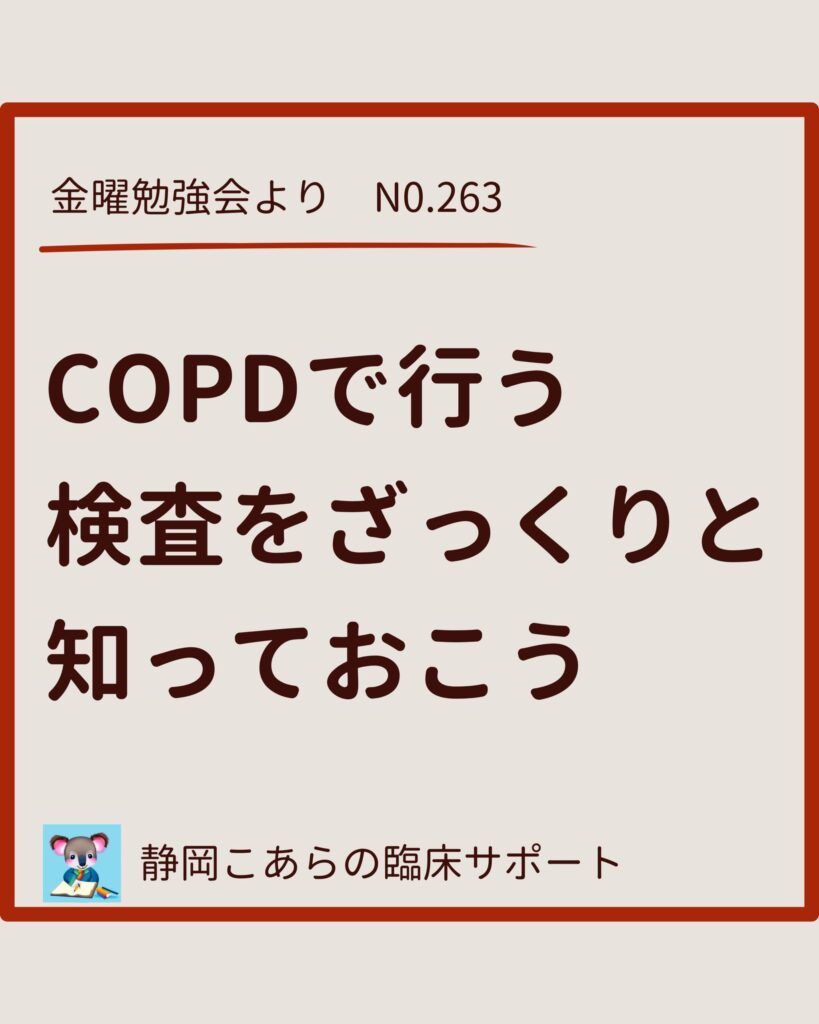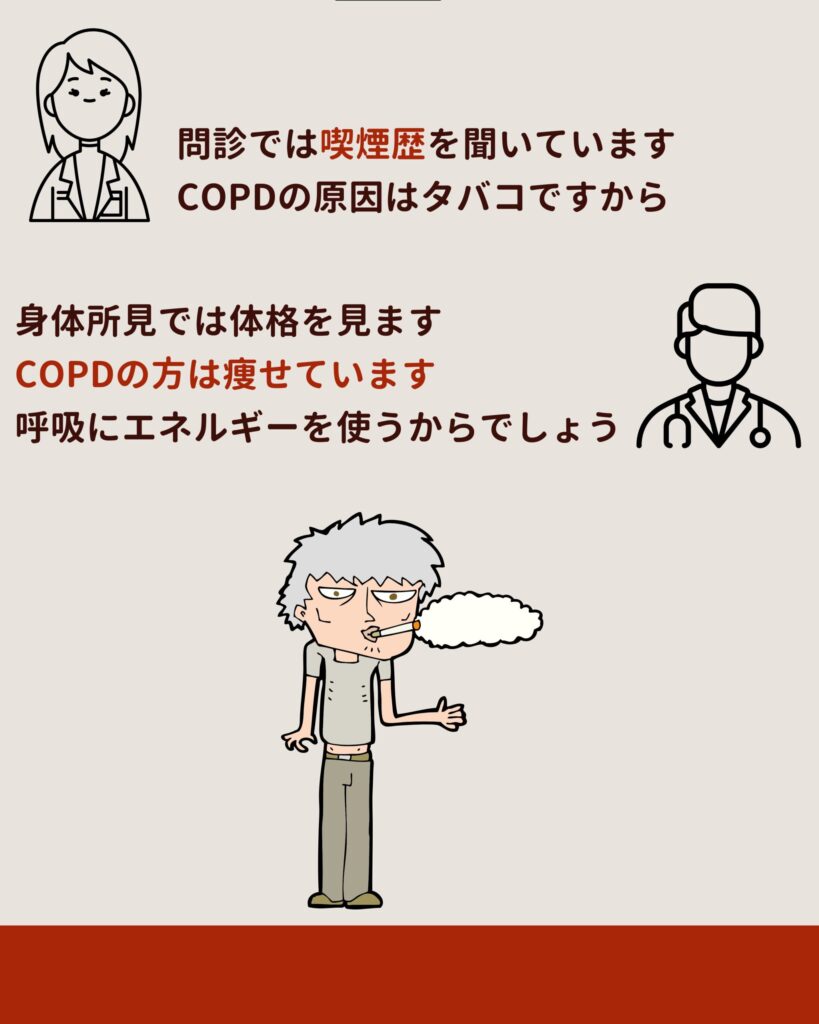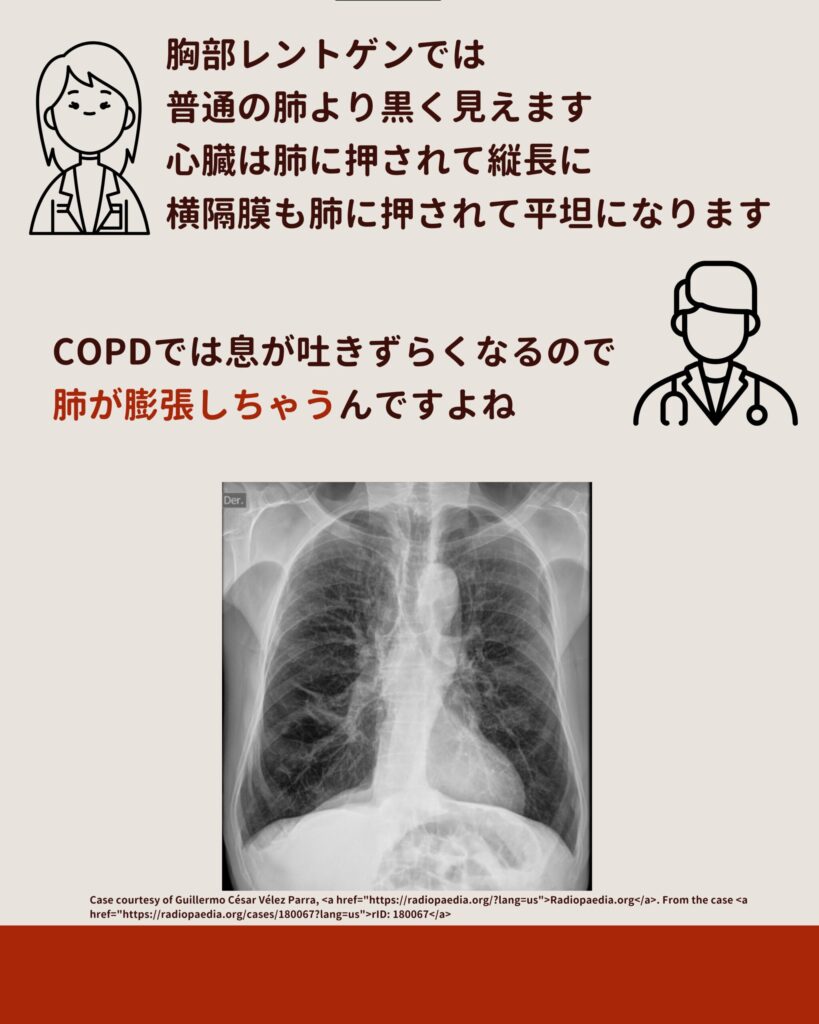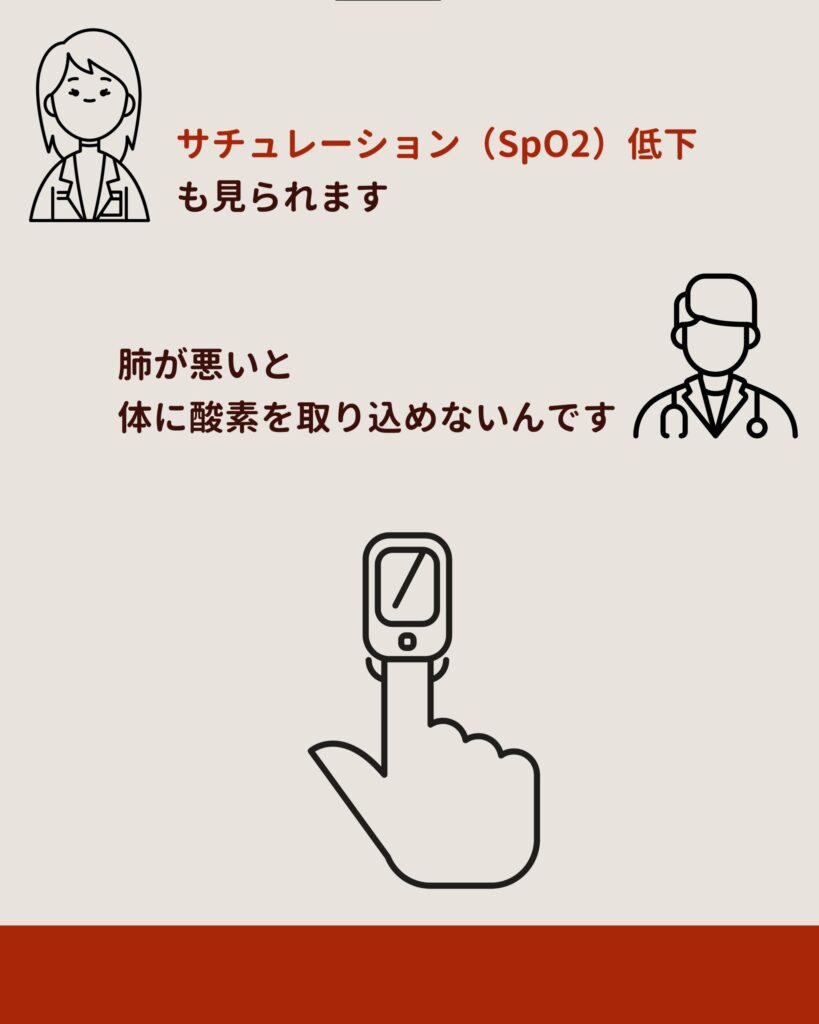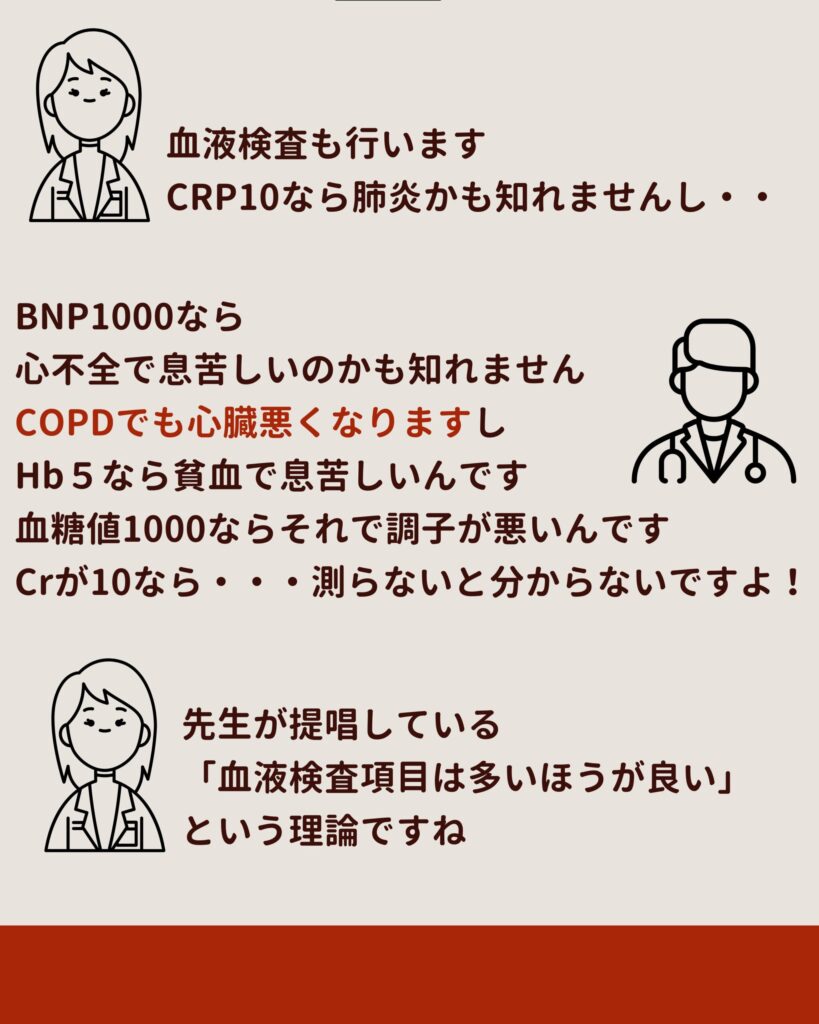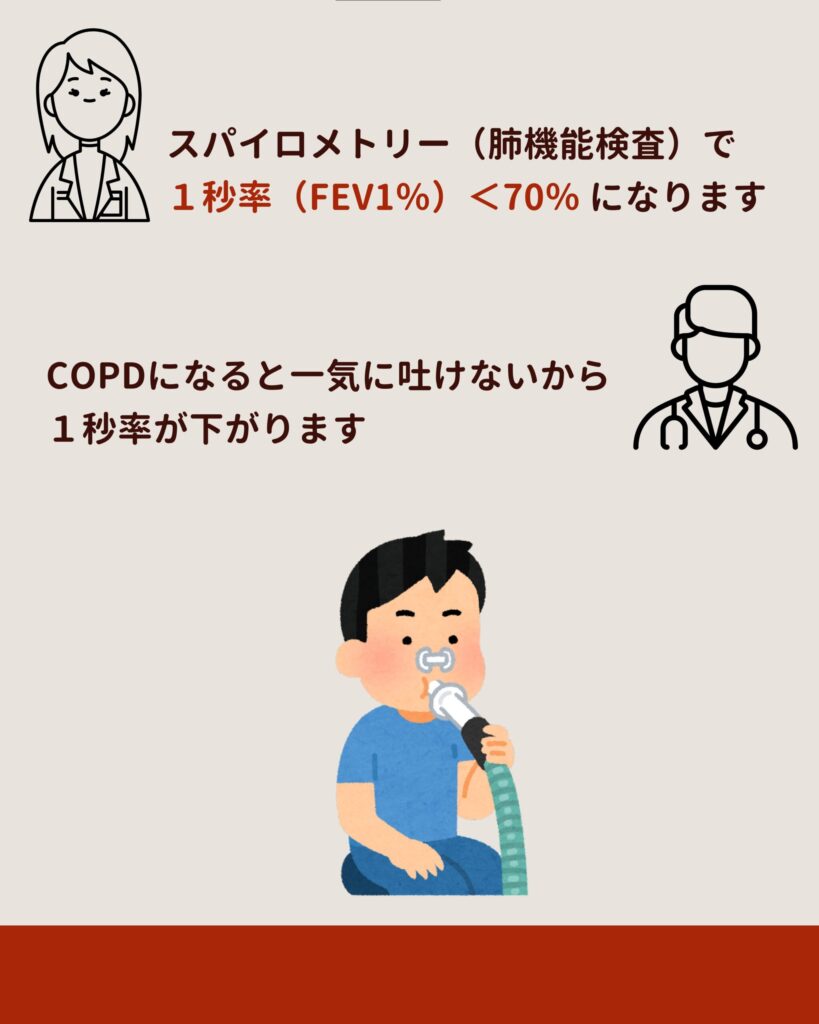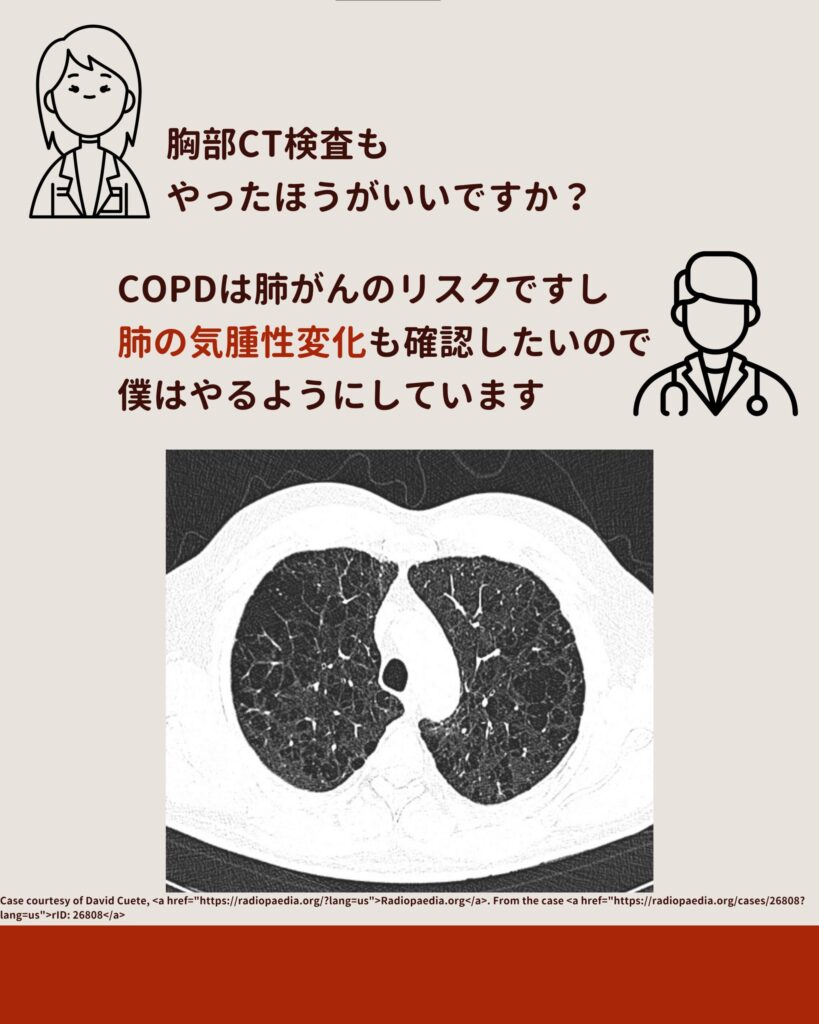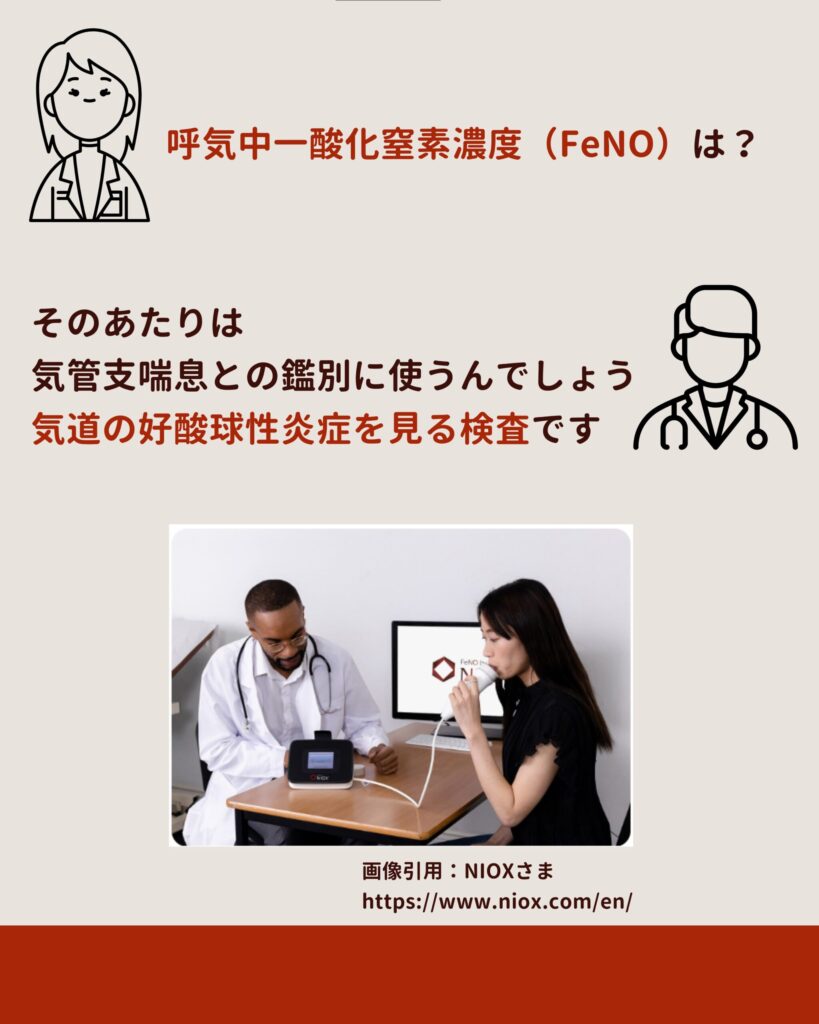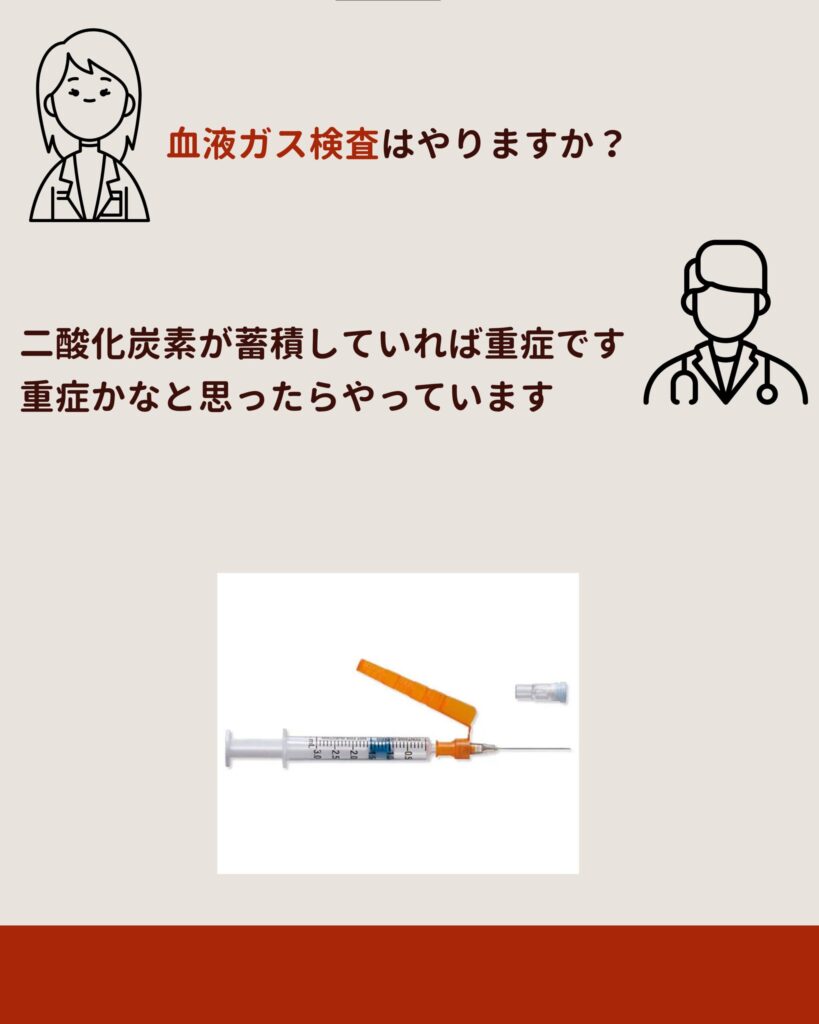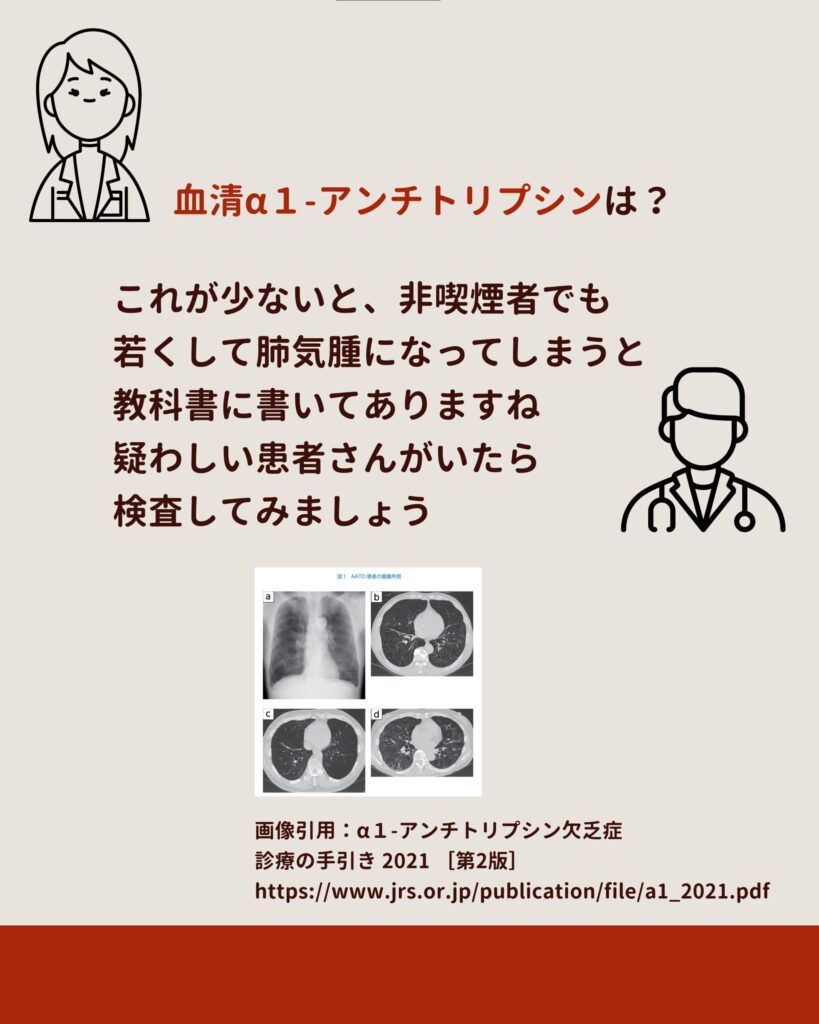慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease:COPD)は、
超簡単に言うと「煙草で肺が壊れる病気」です。
僕が研修医の頃は「肺気腫」と「慢性気管支炎」に分けていたように思います。
いつの間にか「COPD」という呼称が定着し、
最近では「気腫合併肺線維症」や「喘息合併COPD」といった新しい分類も使われるようになっています。
(1)問診と身体所見
問診では喫煙歴を必ず確認します。
COPDの原因のほとんどは喫煙です。
身体所見では体格もチェックします。
進行した患者さんは痩せていることが多く、
呼吸そのものにエネルギーを消費しているためだと考えられます。
(2)胸部レントゲン
胸部レントゲンでは、肺が通常より黒く、心臓は縦長に、横隔膜は平坦になります。
息が吐きづらくなることで肺が膨らんでしまうためです。
(3)SpO₂(サチュレーション)
酸素飽和度(SpO₂)の低下も見られます。
肺が悪くなると、体に十分な酸素を取り込めなくなります。
(4)血液検査
息苦しさの原因が肺だけとは限りません。
CRPが高ければ肺炎、BNPが高ければ心不全、Hbが低ければ貧血、
血糖やクレアチニンの異常も重要な手がかりになります。
僕は「血液検査項目は多いほうが良い」という考え方をしています。
測らないと、見えない病気が隠れていることも多いからです。
(5)スパイロメトリー(肺機能検査)
COPDの診断の中心となる検査です。
1秒率(FEV₁%)が70%未満であれば閉塞性換気障害と診断されます。
一気に吐けないことが、COPDの特徴です。
(6)胸部CT検査
COPDは肺がんのリスクを高めます。
また、気腫性変化の分布を確認するうえでも有用です。
僕はCTでの確認をルーチンにしています。
(7)呼気中一酸化窒素濃度(FeNO)
FeNOは喘息との鑑別に役立ちます。
気道の好酸球性炎症を見ている検査で、喘息合併COPDの診断にも用いられます。
(8)血液ガス分析(ABG)
二酸化炭素が蓄積しているかを確認します。
CO₂が高ければ重症と考え、必要に応じて在宅酸素療法も検討します。
(9)血清α₁-アンチトリプシン
非喫煙者でも若くして肺気腫を発症することがある「α₁-アンチトリプシン欠乏症」。
教科書的にはまれですが、疑わしい場合は検査してみる価値があります。
秘書ユナのコメント
COPDの検査は多いように見えますが、どれも意味があります。
スパイロメトリーで呼吸機能を見て、CTで肺の構造を確認し、
FeNOやα₁-アンチトリプシンで他疾患を除外する。
「息苦しさの正体を探る臨床」という先生の言葉に、すべてがつながります。
前提・分析・結論
(前提)
COPDは喫煙を主因とする慢性呼吸器疾患であり、病態把握には多面的な検査が必要。
(分析)
画像・機能・血液・ガス・炎症など、異なる角度から評価することで、
他疾患との鑑別と重症度判断が可能になる。
(結論)
検査の目的は「正確な診断」だけでなく、
患者の息苦しさの背景を丁寧に読み解くことにある。
インスタグラムならこちら