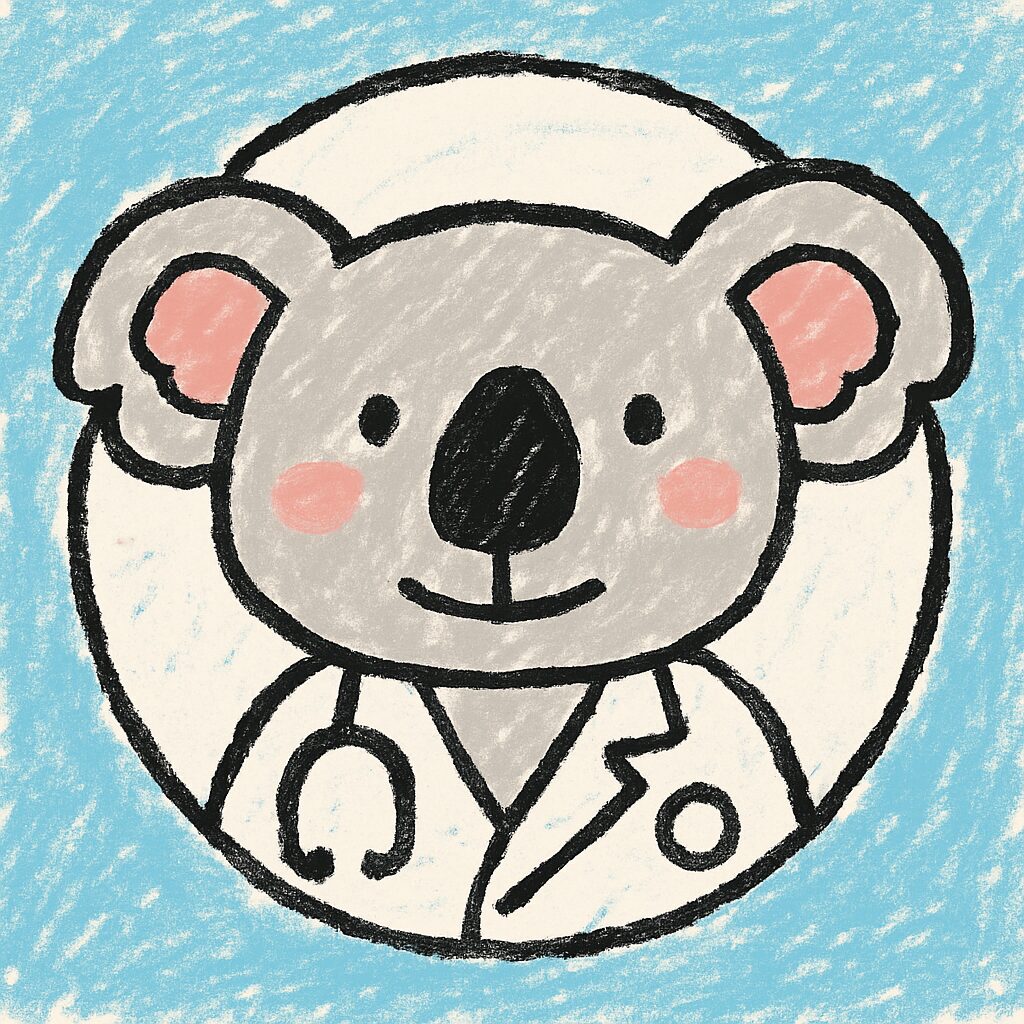本日、浜松で開催された玉置浩二のコンサートへ行ってきた。
今回の公演は、9月に体調不良で中止となった公演の振替である。
正直に言えば、僕は何か一言あるのだろうと思っていた。
中止になった経緯に触れ、迷惑をかけたことを詫び、それでも来てくれたことへの感謝を伝える。自分が同じ立場なら、きっとそうしてしまう。多くの人にとって、それが自然な振る舞いだろう。
けれど、玉置浩二は何も言わなかった。
中止の件にも触れず、事情の説明もなく、謝罪もない。ただ、1曲目から歌が始まった。しかも、その歌は最初から迷いがなかった。
その瞬間、僕は少し戸惑った。
これは、不親切なのだろうか。
それとも、別の誠実さなのだろうか。
僕はこの夜、アクトシティ浜松の大ホール、5階席の最後列にいた。ステージ上の彼の姿は、正直言って、豆粒ほどにしか見えない。表情も細かな仕草も分からない。それでも、歌声だけは違った。距離で薄まることなく、音程も、声量も、響きも、一直線に届いてくる。ホールの最奥にいる自分が、最初から計算に入れられている。そんな感覚があった。
2時間近い公演のなかで、一度だけ彼が大きく視線を上げた瞬間があった。そのとき、なぜか目が合ったような気がした。もちろん気のせいだろう。それでも、「一番遠い席にいる人間にまで、歌を届け切る」という意思だけは、確かに伝わってきた。
玉置浩二は、何かを教えてくれる人ではない。
音楽論を語らず、歌い方を説明せず、チームを作ることも、後進を育てることも語らない。それでも、プロの表現者は皆、彼を見ている。学ぼうとしているというより、自分の現在地を、黙って突きつけられている。
この構図は、医療の現場でも、ときどき目にする。
まだ自分が何者でもない段階で、教育を語り、将来像を語り、マネジメントに話題を移す。それが悪い、という話ではない。ただ、言葉が先に出てしまう瞬間は、誰にでもある。僕自身も、例外ではない。
玉置浩二は、その逆を選んでいるように見えた。
まず、今日の自分を出す。説明はしない。理解されなくても構わない。受け取るかどうかは、聴き手に委ねる。その代わり、逃げ場のない完成度だけが、そこに置かれる。
アンコールで、彼は小さく「もうちょっと歌おうか」と言った。
そのあとに始まった弾き語りは、たしかに優しかった。ただ、その優しさは、甘やかしではない。終盤であっても、声量も、音程も、表現力も、すべてが余裕をもって保たれている。つまり、彼自身が強い。自分の力が揺らがないからこそ、他人に対して、やさしく振る舞える。
今夜、玉置浩二は何も語らなかった。
けれど、語らなかったことで、考えさせられたことは、むしろ多かった。言葉で整えなくても、到達点そのものが示されることがある。その事実を、静かに突きつけられた夜だった。